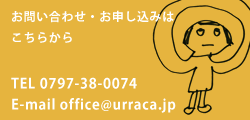家族や友人が知っておきたいPTSDへの理解とサポート

「なんでわかってくれないの?」——PTSDとすれ違う心
恵(めぐみ)さん(仮名・30歳)は、2年前に交際相手から暴力を受けていた経験があります。
暴力はある日突然始まったわけではありません。最初は少し怒鳴る程度だった彼が、だんだんと物を投げ、壁に叩きつけるようになり、最後には彼女の腕を強く掴んで離さなくなりました。
やっとの思いで別れた後、時間が経って今の夫・直樹さんと出会いました。穏やかで優しい人。最初は安心感があり、もう大丈夫だと思っていたはずなのに——。
ある日、ちょっとしたことで直樹さんの声が少しだけ強くなったとき、恵さんの中で“何か”がスイッチのように入ってしまいました。
頭の中が真っ白になり、体が動かなくなり、その場で震え出してしまったのです。
「なに?俺、怒鳴ったりしてないよ?」
直樹さんは困惑した様子でそう言いました。
恵さんも自分の反応に驚き、説明しようとしても言葉が出ません。
それからというもの、ふたりの間に微妙な“距離”が生まれました。
恵さんは罪悪感を抱え、直樹さんは「どうしてあんなふうになるのか分からない」と悩み始めています。
「なんでわかってくれないの?」
恵さんの心の中の叫びは、誰にも聞こえていないように感じられました。
(架空の事例です)
PTSDとは?——“心の傷”が日常に影を落とす
恵さんのように、「もう終わったはずの出来事なのに、体や心が勝手に反応してしまう」ことは、PTSD(心的外傷後ストレス障害)という状態で説明できます。
PTSDとは、命の危険を感じるような強い恐怖や衝撃的な体験の後に起こる、心と体の反応のことです。
戦争や災害だけでなく、DV、事故、性被害、虐待、いじめなど、さまざまな状況がきっかけになります。
代表的な症状には、こんなものがあります:
- フラッシュバック:過去の出来事が、まるで“今起きていること”のように突然よみがえります。音、匂い、言葉などが引き金(トリガー)になることも。
- 過覚醒:ちょっとした物音や人の声にも過敏に反応し、つねに神経が張りつめているような状態になります。
- 回避:過去の出来事を思い出させる場所や人、話題を避けるようになります。結果として、外出や人付き合いが困難になることも。
- 感情の麻痺や孤立感:うまく泣けない、嬉しいと感じにくい、誰にも理解されていない気がする、といった感覚に悩まされることがあります。
PTSDのつらさは、見えづらいからこそ誤解されやすく、本人も周囲も戸惑いがちです。
なぜ、家族やパートナーとすれ違ってしまうの?
「どうして普通にできないの?」
「もう過去のことなんだから忘れたらいいのに…」
そんな風に思ってしまった経験がある人もいるかもしれません。けれど、PTSDの症状は“忘れようとしても勝手によみがえってくる”もの。意思や努力ではどうにもならないのが、この障害の難しさです。
支える側が意図せずかけた言葉や態度が、相手にとっては「攻撃」や「見捨てられた」という感覚を呼び起こすこともあります。
一方で、PTSDを抱える本人も「また迷惑をかけてしまった」と自分を責め、距離をとってしまう…。
こうして、互いに苦しいのに“どうしてもわかり合えない”という状況が生まれてしまいます。
悪気はなくても、PTSDの人を傷つける言葉たち
PTSDを抱える人と接するなかで、「励まそう」「元気づけよう」と思ってかけた言葉が、逆に相手を追い詰めてしまうことがあります。
ここでは、つい言ってしまいがちな言葉と、その背景を紹介します。
「もう終わったことなんだから、忘れようよ」
この言葉は、たしかに前向きに感じられるかもしれません。けれど、PTSDは“過去の出来事”が、今も続いているように感じられてしまう状態です。
恵さんのように、ちょっとした声のトーンや表情が、かつての恐怖をフラッシュバックさせることもあります。
「忘れる」という選択肢が、本人の意思では選べない——それがPTSDなのです。
「気のせいだよ」「大げさに考えすぎじゃない?」
不安や過敏さ、涙や沈黙。それらの反応が、周囲からすると「ちょっと過剰じゃない?」と思えることもあるかもしれません。
でも、それは“今の現実”と“本人が感じている現実”にズレがあるだけ。
本人にとっては、体が危険に反応している状態です。
その感覚を否定されると、「自分がおかしいんだ」と思い込み、ますます孤立してしまいます。
「自分だけがつらいと思わないで」
この言葉も、時に言いたくなってしまうかもしれません。
支える側も疲れていて、悲鳴をあげそうになる瞬間があります。でも、この言葉は、相手に「苦しむことも許されない」という無言の圧力になってしまいます。
もちろん、支えるあなたの苦しさは、とても大切です。
けれどそれは、「相手を責める言葉」にするのではなく、「自分の気持ちとして表現する」形にできると、関係性が保たれやすくなります。
「思い出したくないなら、話さない方がいいよ」
過去の体験に触れないようにすることが、一見“優しさ”に見えることもあります。
けれど、本人が話そうとしているときには、無理に止めるのも逆効果です。
安心できる空間の中で話すことは、回復の一歩になることもあります。
「どうして話したいのか」「今、話せることと話せないことがある」——そんな気持ちに寄り添うことが、大きな支えになります。
誰でも、つまずきながら関わっていく
ここまで紹介した言葉や行動、どれかひとつでも思い当たることがあるかもしれません。
でも、それはあなたが「悪い」わけではありません。それだけPTSDという状態が、理解しにくく、複雑なものだということです。
大切なのは、「間違ってしまうこと」を怖れすぎないこと。
そして、少しずつ学び、やり直していくことです。
家族や友人が「できること」——安心を届ける5つのサポート
PTSDを抱える人を支えるのは、簡単なことではありません。
でも、ほんの少しの理解や気づかいが、その人にとっては「大丈夫だよ」と言ってくれているような支えになることがあります。
ここでは、家族や友人としてできること・してあげられることを5つの具体的なかたちで紹介します。
1. 「話を聞く」よりも、「一緒にいる」を大切に
「話を聞こう」と頑張りすぎる必要はありません。
相手が話したいと思ったときに、ただそばにいて、否定せずに耳を傾ける。それだけで、十分な支えになります。
言葉よりも大切なのは、「安全だと感じられる関係性」です。
沈黙でも、うなずくだけでもいい。話せる・話せないは、本人のタイミングにまかせて大丈夫です。
2. 「安心できる環境」を一緒に整える
PTSDの人は、日常の中で突然フラッシュバックや不安発作に襲われることがあります。
そうしたときのために、静かな空間や安心できる“逃げ場”を確保できると安心です。
大きな音や強い光、人混みなどの刺激を避けたり、「つらくなったら別の部屋に行ってもいいよ」と伝えたりするのも、やさしい配慮です。
3. 「トリガー(引き金)」を一緒に探して理解する
どんな言葉や状況がPTSDの症状を引き起こすのかは、人によって異なります。
相手が「この話題は避けたい」「こういう音が苦手」と伝えてくれたときには、それを尊重してあげてください。
「どうしてそんなことがトリガーになるの?」と聞き返すのではなく、
「そうなんだね、気をつけるね」と受け止める姿勢が、安心を広げます。
4. 「日常のリズム」を一緒に保つサポート
PTSDの症状で睡眠や食事のリズムが乱れると、さらに心身のバランスを崩しやすくなります。
朝の挨拶、食事の声かけ、軽い散歩への誘いなど、ごく普通の“日常”を共有することが、とても大きな支えになります。
何か特別なことをしようとしなくていいのです。
「一緒にごはん食べようか」「今日はよく晴れてるよ」そんな一言が、生きるリズムを取り戻す力になります。
ただ、PTSDの症状などで、どうしても動けないこともあるので、無理に誘うことはしない方がいいでしょう。
5. 「あなたのままでいい」と伝えること
PTSDを抱えている人は、「迷惑をかけている」「周りに理解されない」と感じて、自分を責めがちです。
そんなときに、「大丈夫、あなたはあなたのままでいいよ」と、存在を認めてくれる言葉は、何よりの癒しになります。
無理に元気づける必要はありません。ただ、「ここにいていい」と伝えてあげてください。
小さな関わりが、大きな支えになる
誰かの痛みに寄り添うということは、その人を“治そう”とすることではなく、“そのままの存在”として一緒にいることです。
できることは、たしかに限られているかもしれません。
でも、その限られた関わりが、苦しんでいる人にとって「生きていてもいいんだ」と感じさせてくれることもあります。
専門的な助けを求めるタイミングと方法
どんなに家族や友人が頑張っても、PTSDは一人で抱えきれるものではありません。
本人にも、支える側にも限界があります。
だからこそ、専門家のサポートを受けることは「弱さ」ではなく「回復への第一歩」です。
でも、「どこに相談したらいいの?」「いつ相談したらいいの?」と迷う人も多いのではないでしょうか。
ここでは、専門的な支援が必要になるサインと、実際の相談先・つなぎ方をご紹介します。
こんなサインがあったら、迷わず相談を
次のような状態が数週間〜数ヶ月にわたって続いている場合は、医療機関やカウンセラーへの相談を検討しましょう。
- 毎晩のように悪夢を見る/眠れない日が続く
- 急に怒りっぽくなったり、感情の波が激しくなっている
- フラッシュバックや過呼吸、動悸などが頻繁に起こる
- 外出できない、人と関われないなど、生活に支障が出ている
- 「死んだほうが楽かも」と思うことが増えてきた
- 支える側も疲れ切ってしまい、日常がままならない
本人が相談を拒んでいる場合も、まずは支えている家族・友人自身が専門家に相談することが大切です。
どこに相談すればいい?
■ 精神科・心療内科
まずは医師による診断を受けることで、症状に合った治療方針を立ててもらえます。薬物療法が必要な場合もあります。
■ カウンセリング(臨床心理士・公認心理師など)
話を丁寧に聴いてくれる専門家が、安心できる関係の中で心の整理や回復のプロセスをサポートします。
カウンセリングは、PTSDを抱える本人が「安心して自分の気持ちを話せる場所」として、とても大切な役割を果たします。
臨床心理士や公認心理師といった専門家は、決してアドバイスや説教をするのではなく、その人のペースを大切にしながら、丁寧に話を聴くことに重きを置いています。
PTSDの症状は、「話すのが怖い」「自分の気持ちがわからない」「何から伝えたらいいのかわからない」といった状態に陥りやすいものです。カウンセリングでは、そのような状態でも無理をせず、今の自分に起きていることを、少しずつ“言葉にしていく”手助けをしてくれます。
カウンセリングには次のようなメリットがあります。
- 感情や記憶を整理できる
つらい記憶を無理に語らなくても、安心できる関係の中で少しずつ心の奥にある感情を整理していくことができます。 - 安心・安全な関係性を体験できる
過去の人間関係で深く傷ついた方にとって、「否定されない」「急かされない」関係性は大きな癒しになります。 - “自分を責める思考”のくせに気づける
PTSDのある方は、「全部自分が悪い」と感じやすくなっています。カウンセリングでは、そうした考え方に気づき、少しずつ距離をとることができます。 - 再発や悪化の予防につながる
症状がぶり返しそうなときも、早めにサインに気づき、対応することで、より穏やかに過ごせる時間が増えていきます。 - “回復のリズム”を取り戻す支えになる
カウンセラーとの定期的な面談は、生活リズムや自己ケアの習慣づけにもつながり、安心できる日々を築くための土台になります。 - また、EMDR(眼球運動を使ったトラウマセラピー)やソマティック・セラピー(からだの感覚を活用したトラウマセラピー)、箱庭・芸術療法など、専門的な心理療法を提供しているカウンセリングルームもあります。
トラウマ・PTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状とカウンセリング
■ PTSDに対応している支援機関・団体
- こころの健康相談統一ダイヤル(厚生労働省)(0570-064-556)
- 神戸市精神保健福祉センター
- くらしとこころの総合相談会(ハローワーク神戸において弁護士によるくらしの相談、保健師・心理士等によるこころの相談を実施しています)
- 兵庫県こころのケアセンター(事件・事故・災害等によるトラウマ・PTSD等に関する研究や研修、相談・診療などを行っています。診察には医療機関からの紹介が必要です)
- ひょうご被害者支援センター(犯罪等の被害者やそのご家族を精神的に支援する民間の支援団体)
- ひょうご性被害ケアセンターよりそい(性暴力被害を受けた方のワンストップ支援センター)
- NPO法人フェミニストカウンセリング神戸(セクシュアルハラスメント、ドメスティックバイオレンス(DV)、性虐待、性暴力など「女性への暴力」被害にあった女性をサポートしています)
- 兵庫県警察 被害者支援室(サポートセンター)
専門家への“つなぎ方”に迷ったら
「病院に行こうって言い出しにくい…」
「本人が拒否してしまう…」
そんなときは、無理に“説得”しようとしないことが大切です。
代わりに、こんなふうに伝えてみてください:
「ちょっと気になってて、一緒に話を聞いてもらえないかな」
「私も一度相談してみたいと思ってて、ついてきてくれる?」
「怖いと思うけど、ここまで頑張ってきたんだし、少しだけ頼ってみてもいいと思うよ」
まずは家族が先に相談することで、本人が安心して「行ってみようかな」と思えることもあります。
支えるあなたも、無理をしないで——「ケアする人のケア」という視点
PTSDを抱える人を支えているあなた——
その優しさ、根気、そして葛藤を、誰かがちゃんと見ていてくれることはありますか?
「自分がしっかりしなきゃ」
「私が弱音を吐いてはいけない」
そう思えば思うほど、あなた自身の心も、知らず知らずのうちに疲れ果てているかもしれません。
「支える側のつらさ」は、見えにくく・気づかれにくい
PTSDを抱える人と過ごす日々は、繊細な気づかいや忍耐を必要とします。
感情の起伏に巻き込まれたり、自分の思いが通じない孤独を感じたりすることも少なくありません。
でも、「相手のほうがつらい」と思って、自分の気持ちを後回しにしてしまう方がとても多いのです。
それはまるで、酸素マスクを相手にだけ着けようとして、自分が息切れしてしまうようなもの。
支えるあなたにこそ、ケアが必要です
本当に相手を支えるには、まず自分の心に余裕があることが大切です。
だから、こんなことを「わがまま」や「甘え」だと思わないでください:
- 一人になる時間を持つ
- 信頼できる誰かに気持ちを話す
- カウンセラーや相談窓口を活用する
- 好きなことをする、小さな楽しみを見つける
- 「今日はできない」と言う
あなたがちゃんと呼吸できるようになってこそ、誰かの隣に立ち続けることができるのです。
支援者向けのサポート資源も活用しましょう
最近では、「家族のためのカウンセリング」や「ピアサポートグループ」なども増えてきています。
- 精神保健福祉センターや地域の保健所
- PTSD対応の民間カウンセリングルーム
- 当事者・家族会、NPO団体のグループ相談など
自分だけで抱えこまないこと。誰かに話すことは、あなたが折れないための“ケアの選択”です。
おわりに:関係性の中で、少しずつ回復していく
PTSDは、本人だけの問題ではありません。
それを支える家族や友人もまた、関係性の中で深く揺さぶられ、試されるものです。
でも、決してあなたは一人ではありません。
知ること、理解しようとすること、小さなサポートを積み重ねること。
そのすべてが、相手にとっても、あなた自身にとっても、かけがえのない“支え”になっています。
ゆっくりで大丈夫。
できることから、少しずつ一緒に歩いていきましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1:PTSDって、本人が「気持ちを切り替えれば」治るものですか?
いいえ。PTSDは気持ちの持ちようではなく、脳や神経の働きにも関係する心の傷です。本人の努力だけで乗り越えるのは難しく、周囲の理解や専門的な支援が必要です。
Q2:つらそうにしているのに、何も話してくれません。無理に聞いたほうがいいですか?
無理に聞き出すことは避けたほうがよいでしょう。話すこと自体がつらくなる場合もあります。まずは、話したいときに安心して話せる雰囲気を作っておくことが大切です。
Q3:「また調子が悪くなったの?」とイライラしてしまう自分が嫌です。
そう感じるのは自然なことです。支える人も疲れたり、混乱したりするのは当たり前です。自分の気持ちにフタをせず、誰かに相談したり、距離をとることも大切な選択です。
Q4:どこまで関わればいいのか、線引きがわかりません。
自分ができる範囲を明確にすることが大切です。すべてを背負おうとすると、支える側も限界を超えてしまいます。無理のない関係を保つことが、長く支え続けるための土台になります。
Q5:家族として、通院やカウンセリングに同伴したほうがいいですか?
本人が希望する場合は、ぜひ同伴してあげてください。特に初めての受診や相談は不安が大きくなることが多いです。ただし、一人で行きたいという気持ちがあるときは、それを尊重してあげてください。
Q6:薬に頼るのはよくないと聞いたのですが、本当ですか?
薬物療法は、必要に応じて取り入れられることのある大切な治療の一部です。不安や不眠などの症状が強い場合、薬によって心身の安定をはかることができます。主治医とよく相談しながら決めていきましょう。
Q7:良くなっても、また再発することはありますか?
あります。PTSDは波のある回復過程をたどることが多く、再発することもあります。でも、それは失敗ではなく、また新しく整えていくための一歩です。回復には時間がかかることもありますが、支える関係性があることで、再び落ち着きを取り戻すことができます。