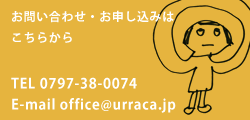『そういうゲーム』ーメタ認知で心の柔軟性を高める
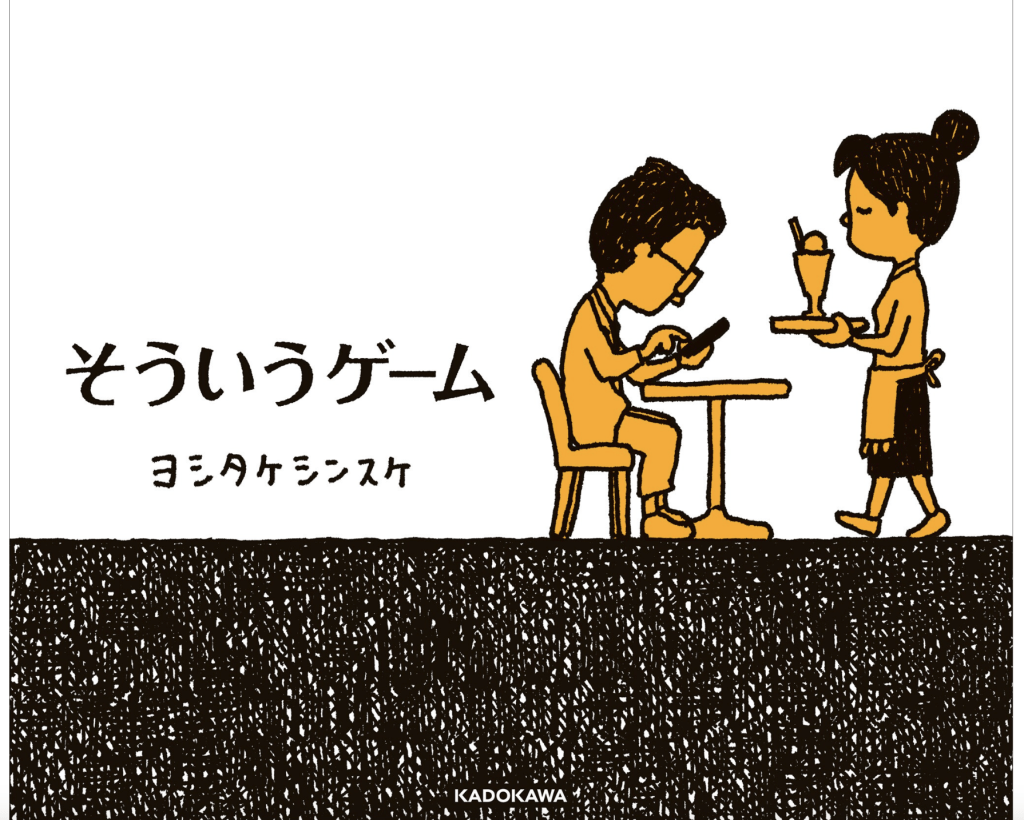
先日、ある司書さんから紹介していただいて、読んでみた絵本です。
ヨシタケシンスケさんの絵本『そういうゲーム』。
ちょっと面白かったのでここでも紹介してみますね。
この本には、日常のささいな出来事や、生きるうえで避けられない苦しみを「そういうゲーム」として受け止める人、とくに、日々を「なんとかやり過ごしている」ような人たちにとって、この本のやさしくて少し切ない視点は、そっと寄り添ってくれるものがあります。
この本には、日常のささいなことを「ゲーム」に見立てて乗り切っていこうとする男の人が出てきます。
その“ゲーム”は、こんなふうに描かれています。
おうだんほどうの 白いところだけふんで
むこうがわまでいけたら かち。
おちたらワニがいる。そういうゲーム。
子どもの頃によくやった遊びのようですが、大人になっても、こんなふうに目の前の現実を「ゲーム」に見立ててみるだけで、少し気持ちが軽くなることがあります。
つらいことも「これはそういうゲームなんだ」と思えるだけで、感情にのまれずにすむことがあるのです。
実はこの「そういうゲーム」とつぶやく行為は、心理学でいう「メタ認知」にとても近いものです。
メタ認知とは、自分の思考や感情に気づき、それを一歩引いて観察する力のことです。
怒っている自分に気づいたり、考えすぎていることを自覚したりする“もう一人の自分”が現れるとき、そこにはメタ認知が働いています。
この絵本には、もっと深いところでの「ゲーム」も登場します。
自分を傷つける人から どこまでとおくにいけるかどうか
そこそこ いごこちのいいばしょを
みつけることが つくることができるかどうか。そういうゲーム。
これは、まさに大人のサバイバルです。
完璧な環境や関係を手に入れることではなく、そこそこ居心地のいい場所を、自分なりに見つけること。
この“そこそこ”という感覚が、とても現実的でやさしい。
心理学では、こうした心の持ち方を「心理的柔軟性」と呼びます。
状況に応じて自分を守り、ちょっとだけマシな選択をしていく力です。
そして、こんなふうにも描かれています。
つらいとき、想像力だけを使って
手のひらに小さな人が見えるようになるかどうか
その人とたのしくおしゃべりできるようになるか。そういうゲーム。
これは、自分の内側に「味方」をつくる力です。
心理学で言えば、「内的対象」や「想像的対話」に近い考え方です。
苦しいとき、自分の中に支えてくれる存在を想像できるというのは、回復力やセルフケアの力として、とても大切なものです。
こうした“ゲーム”を通して、ヨシタケさんは「うまくやること」ではなく、「どうやって生きのびるか」という問いを、やわらかく、ユーモラスに提示しています。
そして、それを「ゲーム」ということばにすることで、ほんの少し、距離が生まれます。
のまれそうだった感情に、ちょっとだけ余白ができて、自分を眺めるスペースが生まれるのです。
これは、仏教の「サティ(念)」にも似ています。
サティとは、今この瞬間に起きていることに気づき、判断せずに見つめる態度のことです。
ヨシタケさんの「そういうゲーム」は、現代の言葉で語られる“気づきの実践”なのかもしれません。
怒り、悲しみ、落ち込み――そうした感情に飲みこまれそうなとき、
「ああ、これはそういうゲームなんだな」と心の中でつぶやいてみること。
それは、自分を責めるかわりに、自分を見守るための、
とても静かで、やさしい言葉になるはずです。