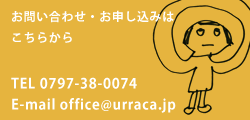統合失調症の治療とカウンセラーの役割:臨床心理士の視点(心理テスト・心理教育・カウンセリング)
単科の精神病院で30年以上、臨床心理士・公認心理師として多くの統合失調症の患者さんやご家族と向き合ってきました。この経験をもとに、統合失調症の治療におけるカウンセラーの具体的な役割と、その重要性について詳しく解説します。
統合失調症治療の現状と心理士の関わり
現在、統合失調症の治療の中心は薬物療法です。特に急性期には入院が必要となるケースも少なくありません。しかし、薬物療法だけではカバーしきれない部分が多く、そこに私たち心理士が関わる意義があります。
主に以下の場面で、統合失調症の方のサポートを行っています。
1. 心理検査・アセスメント
外来や入院中の患者さんに対して、心理テストを実施し、病状や認知機能のアセスメントを行います。
よく使用する心理検査は以下の通りです。
- ウェクスラーの知能検査(WAIS):知能や認知特性を評価します。
- バウムテスト:描画を通して内面を探ります。
- ロールシャッハテスト:心の動きや体験世界、他者との関わり方などを深く理解するために有効です。
- MMPI(ミネソタ多角的パーソナリティ目録):性格特性や精神状態を多角的に評価します。
特にロールシャッハテストは、「精神病圏かどうか微妙なケース」の鑑別によく用いられ、その人の体験世界や身の守り方を推測する上で多くの示唆を与えてくれます。
2. カウンセリング
主治医が必要と判断した場合、カウンセリングを行います。特に急性期の症状が落ち着き、日常生活を送れるようになった後も、家族関係や人間関係、その他の悩み事や困り事がある場合に紹介されることが多いです。
統合失調症の方にとって、不安が重なると幻聴や妄想が強まることがあります。そうした際に、丁寧に話を聞き、その方のリソース(強みや資源)や安心できることを一緒に見つけ、具体的な対処法を検討することで、症状が落ち着くケースが多々あります。
かつての精神医学の教科書には、「幻聴や妄想にカウンセリングは効果がない」と書かれていることもありました。しかし、近年の統合失調症の治療の進歩(薬物療法の強力なサポートなど)や、オープンダイアローグのような対話重視のアプローチの台頭により、対話によって安心感が得られ、陽性症状が軽減する事例がよく見られるようになっています。
3. デイケアでのグループ活動
病院に新設されたデイケアでは、長期間にわたりグループ活動を担当してきました。主に統合失調症の方々を対象に、様々な活動を行っています。
- 調理活動:たこ焼き、お好み焼き、パン焼き、ガトーショコラ作りなど、共同作業を通じて楽しみながら交流を深めます。
- ソーシャル・スキル・トレーニング(SST):男性グループでの「逆バレンタイン」企画のように、実践的なコミュニケーション能力の向上を目指す活動も行いました。
- 文化・レクリエーション活動:水鉄砲合戦、ハンモックでの昼寝、野点での連句作り、演劇、映画制作(iPhoneのみで撮影から編集まで!)など、遊びを通して自己表現や協調性を育みます。
- 心理教育・当事者研究:病気への理解を深め、自分自身の体験を探求する真面目なセッションも実施します。
経験上、メンバーさんが楽しんで取り組める「遊び」の要素を取り入れた活動は、得るものも大きいと感じています。
4. 家族心理教育グループ
統合失調症の患者さんのご家族を対象とした心理教育グループも長く担当しています。
「標準版家族心理教育」というプログラムに沿って、ご家族の抱える困り事や悩み事をグループで共有し、話し合います。セッションは以下のように構造化されており、参加者も安心して話しやすい環境です。
- 心理教育と情報提供の講義
- チェックイン(現在の状態や気持ちの共有)
- 取り上げたい困りごとの提示
- 今日のテーマを選ぶ
- テーマについて質問し、詳細を共有する
- アイデアや工夫の提案
- 実践できそうなこと、試してみたいことの選択
- メンバーからの一言メッセージ
5. 統合失調症の精神療法・認知療法
原田誠一著の『統合失調症の治療 理解・援助・予防の新たな視点』(金剛出版、2006年)は、統合失調症の精神療法や予防について深く掘り下げた書籍で、私たちの仕事に多くの示唆を与えてくれます。
『統合失調症の治療 理解・援助・予防の新たな視点』原田誠一著、金剛出版、2006年

この本で紹介されている、あるご家族からの手紙には、現在の日本の精神医療に対する切実な思いが綴られています。
「今の精神科の治療では当事者や家族がおきざりになり、病気や治療方針の説明がなされないまま漫然とクスリを飲み続け、ただなんとなく通院している人が多いように思います。他の体の病気のように病気や症状の仕組み・意味を理解させ、病人と家族が自分たちも工夫できるよう、なぜ精神科のお医者さんは指導しないのか、もどかしく感じております」
これは、薬物療法や入院が中心だった日本の精神医療が抱える大きな課題です。私が働き始めた25年前と比べると、グループホームや作業所、訪問看護など、地域での生活をサポートする支援は格段に充実し、オープンダイアローグのような対話によるケアにも注目が集まっています。
「病気や症状の仕組み・意味を理解」し、「病人と家族が自分たちも工夫できる」ようになると、幻聴などの症状の影響力が弱まり、混乱せずに落ち着いて対処できるようになります。
例えば、「正体不明の声 ハンドブック」(http://www.ar-pb.com/files/s_handbook.pdf)には、「正体不明の声が聞こえる」現象は、不安、孤立、過労、不眠が重なったときに起こりやすい、決して珍しくない現象であると書かれています。
こうした知識を得ることで、心配事を相談したり、無理をせずに休んだり、睡眠を改善する工夫をしたりすることが可能になります。
カウンセラーとして統合失調症の方にお会いする際には、これらの情報をわかりやすく伝え、「正体不明の声は気にしないようにする」「信頼できる人に相談する」「楽しい活動をする」「よく休む」といった、その人に合った具体的な対処法を一緒に検討していくことを大切にしています。
まとめ:カウンセラーが目指すもの
統合失調症をはじめとする精神病圏の病態が重い方へのカウンセリングでは、いたずらに深層を探るのではなく、困り事を整理し、見通しを持ち、具体的な対処法を見つけることが何よりも重要だと考えています。
私たち臨床心理士は、薬物療法と連携しながら、患者さんやご家族が安心して日常生活を送り、自分らしい人生を歩めるよう、多角的な視点からサポートを提供しています。
統合失調症に関するお悩みや、カウンセリングについてご質問がありましたら、お気軽にご相談ください。
最終更新日:2025年5月28日