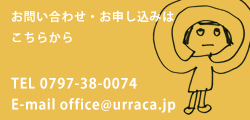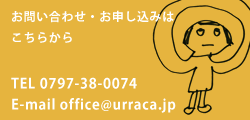心理テストでわかる5つの性格(ビッグファイブ)
「悲観的な性格を治したい」「怒りっぽい性格で損をしている」といったように、「性格」の問題でカウンセリングに来談される方がおられます。
「はたして“性格”というような一貫した傾向があるのか、そんなのは錯覚みたいなものじゃないか」といった意見もあるのですが、日常の仕事や人間関係で「性格」についてしばしば言及されるということは、それなりに有用な仮説だと考えてもいいのではないでしょうか。
ここでは「性格」と、それを測定するための「心理テスト」についてお話しします。
パーソナリティとは
パーソナリティ(性格、人格)は、「その個人の思考・感情・行動の根底にある持続的で一定したパターン」(ICD)あるいは「認知・感情・対人関係の領域にわたる持続的で一貫した傾向」(DSM–Ⅳ)と定義されています。
語源をさかのぼると、「ペルソナ(persona)」という仮面を意味する言葉に由来しています。
ユング心理学では、私たちが外向けに身につけている性格を「ペルソナ」と読んでいます。私たちは、日常生活で「父親の仮面」「母親の仮面」「いい子の仮面」「教師の仮面」「カウンセラーの仮面」といった役割性格をまとって生きているのだという発想です。
おとうさんおとうさん
ぼくのおとうさん
かいしゃへいくと かいしゃいん
しごとをするとき かちょうさん
しょくどうはいると おきゃくさん
という歌がちょっと前にNHKで流れていました(「ぼくのおとうさん」という歌です)。関係や文脈、場面によって「役割性格」は変わってくるということですね。精神科医の中井久夫先生のエッセイに「二重人格はなぜありにくいか」というタイトルの文章があったのですが、そこには確か、日本人は関係性によって一人称や性格が変わり、人格の一貫性を無理に求められないからといったことが書かれていたと思います。パーソナリティの一貫性や責任が強く要求される欧米社会のほうが、「二重人格」が問題となりやすいということです。
全世界が一つの舞台
そして人間はみな役者にほかならぬ
それぞれに出があり引っ込みがあり
一生を通じてさまざまな役を演じる
シェークスピア『お気にめすまま』
こうシェークスピアが書くように、私たちは人生のなかで「さまざまな役を演じる」のです。自分がどんな仮面をつけて舞台に上がっているか、ときどき確かめてみることも大切かもしれません。あまりに仮面が厚くなりすぎたり、外せなくなってしまうと、それはそれで問題なのです。家に帰っても教師の仮面が外せずに、自分の子どもに「先生はこう思うぞ」なんて叱っている親がいたら、ちょっと困りますよね。
古代ギリシャのパーソナリティ論
ローマ帝国時代のギリシャの医師ガレノス(西暦130年〜200年)は、ヒポクラテスの提唱した四大元素を元にした医術を発展させて、独自のパーソナリティ論をつくりました。
ガレノスは、ローマに住みマルクス・アウレリアス帝などに仕え、医術について何百冊もの本を書いたと言います。剣闘士のケガの治療や、動物の解剖によって、生きものの身体の仕組みに関する深い知識を身につけていたのです。
ガレノスによるパーソナリティ論は、体内の「体液」のバランスによって気質が決まるというものでした。体内には、地水火風という四つのエレメントの影響を受けた四種の体液があり、どれかひとつが多くなると、それに関係する気質が支配的になるというのです。
多血質
血液量が多く、気持ちが温かい人柄。楽天的で自信に満ちているが、ときどき自分中心にふるまうこともある。
粘液質
ゆっくり穏やかで、内気な性格。理性的で、自分をしっかりもっている。
胆汁質
黄胆汁が多く、カッとなりやすい。精力的で情熱的な性格。
憂うつ質
黒胆汁が多く、詩的で芸術を好む傾向。繊細なので、悲哀や不安、抑うつを体験しやすい。
といった具合です。
体液の偏りが大きいと、性格も極端に表れやすくなります。あんまり憂うつすぎたり、血の気が多すぎたりすると困るので、そのときには食事を制限したり、血を抜くことなどでバランスが取れるとガレノスは考えました。
後に医学が発展して、ガレノスの学説の間違いが多く発見されたこともあり、彼の気質論も説得力を失っていきました。
しかし、20世紀に発展する心理学のパーソナリティ論に大きな影響を与えているのも事実なのです。いわゆる「タイプ論(類型論)」のご先祖だと言えます。
近代心理学のパーソナリティ理論
クレッチマーの『性格と体型』
ドイツの精神科医エルンスト・クレッチマー(1888~1964)は、統合失調症、躁鬱病、てんかんなどの患者を観察して、体型と性格の関係を論じました(『性格と体型』1921年)。
分裂気質:細長型の体格をしていて、神経質で、刺激や変化に敏感です。内向的で、ときに一風変わったことを考えることがあります。
循環気質:体型は肥満型で、社交的で明るく、人づきあいもいい性格です。しかし、ちょっとしたことで落ち込むなど、気分の浮き沈みが大きいのも特徴です。
粘着気質:筋肉質で引き締まった闘士型の体型です。仕事や課題には精力的に取り組み、徹底的にやりとげないと気が済みません。粘り強さとこだわりが特徴です。
クレッチマーの『体型と性格』は、当時、かなりのベストセラーになりました。科学的根拠が乏しいと否定されたりもしているのですが、用語としては今も精神医学や心理学の現場でときどき使われます。
たぶん、「3タイプで説明しきる」といったシンプルさが、「大雑把に把握したり、伝えたりしたい」といったときに役に立つのだと思います(逆に論文などには使いにくいでしょう)。
ユングのタイプ論
カール・グスタフ・ユング(1875-1961)は、『タイプ論』などの著作で、「内向と外向」などのよく知られているパーソナリティ特性を描き出しました。
ユングのいう外向型(extroversion)とは、心のエネルギーが、お金や地位、他人の評価といった外の世界に向かう人々を指しています。
内向型(introversion)は、心のエネルギーが、信念や自分の感情、価値観などの自己の内部に向かうタイプの人々を表します。
ユングは、外向/内向と、「思考・感情・感覚・直感」を組み合わせることで、8つの性格類型を仮定しました。
たとえば、思考タイプは物事を論理的に考えようとします。感情タイプは、好き嫌いで判断するので、思考の対極に位置づけられます。感覚タイプは、物事を見たままに感じて、緻密に観察しようとします。直感タイプは、物事の本質をぱっとつかもうとします。思いつきやひらめきで動くことが多い人々です。
「内向/外向」などは、現代の5因子理論にも受けつがれています。
ユングのタイプ論は、詳しく見ると、性格理論というよりは、力動的なパーソナリティ理論だと考えられます。パーソナリティは固定したものではなく、意識的な態度や傾向とは正反対のこと(多くは無意識的なものです)をいかに取り入れて全体性を得ていくかが大切だとユングは考えたのです。
タイプA行動パターンとタイプB行動パターン
特定の身体的な病気と性格傾向が関連しているという研究もあります。アメリカの医師フリードマンらは、狭心症や心筋梗塞などの心臓疾患になりやすい性格傾向を「タイプA行動パターン」と名づけました。フリードマンは、循環器科の外来だけ、なぜか待合室の椅子が早くすり切れるのを見つけました。待合室の様子を観察してみると、心臓の病気をもった患者さんたちは、そわそわ、イライラしたようすで、すぐ立ち上がることができるように椅子に浅く腰かけています。そのために椅子の前のところだけ、すり切れるということがわかりました。
ここから、フリードマンは、心臓病患者には特徴的な性格傾向があると考えました。
- 同時に二つのことを考えたり、したりする。
- より少ない時間により多くの活動をしようと計画する。
- 他人の話をせかす。
- 話すとき、身振りをさかんにする。
- たとえ、子どもとゲームをするときでさえ、ほぼどんなゲームでも勝つためにする。
- 自分のほうがうまいし早くできると思うことを、他人がしているのを見ていると、いらいらしてくる。
こんな特徴をもった人たちです(『ヒルガードの心理学』より、いくつか抜粋してみました)。ようするに、競争心が強くてエネルギッシュで、いつも時間に追われているように忙しく行動している人たちです。彼らは、積極的ですが、ときにアグレッシブすぎて怒りっぽくなります。また、せっかちで、いつもたくさんの仕事を抱えています。自分からストレスの多い生活を選んでいるようにも見えますが、ストレスの自覚には乏しいのです。
身体的には、高血圧、高脂血症のことが多く、ストレスが増えて血圧が上がると循環器系に無理がかかって、心臓疾患になりやすいということなのです。
逆に、フリードマンらが「タイプB行動パターン」と名づけた性格特徴をもつ人々は、マイペースでのんびりしており、忍耐強くてあまり怒ったりしません。
研究では、タイプAの人は、タイプBの人と比べて2倍も心臓疾患になりやすいのだと言われています。
興味深いことに日本で行なわれたコホート研究では、男性の場合、「タイプB行動パターン」が「タイプA行動パターン」と比べて、発症リスクが1.3倍高いという結果が得られています(タイプA行動パターンと虚血性心疾患発症リスクとの関連)。タイプA行動パターンの人のほうが、喫煙や飲酒の量が多く、高ストレスであるということは、欧米と同じでした。タイプBの人は、よりストレスを溜め込んでしまうのだろうと推測されています。
女性の場合は、欧米の研究と同じくタイプAのほうがリスクが心臓疾患の発症リスク高く、性差や文化差が影響しているのだろうとのことです。
5因子性格理論(ビッグファイブ)
人のパーソナリティについては、現代では因子分析を使って研究されることが中心になっています。いくつの性格因子に分けるのが適切かということにはさまざまな見解がありましたが、今では「ビッグファイブ」と呼ばれる5つの因子で性格を記述するという考え方が心理学では一般的です。
ビッグファイブの5つの因子は、次のようなものです。
- 神経症傾向(Neuroticism)
- 外向性(Extraversion)
- 開放性(Openness to experience)
- 協調性(Agreeableness)
- 統制性(Conscientiousness)
それぞれ、簡単に説明してみますね。
神経症傾向(Neuroticism)
情緒安定性(不安定性)、情動性などとも訳されることがあります。この傾向が強い人は、外からの刺激に敏感に反応します。神経質で、不安を感じやすいのです。危険に対して敏感なので、行動は慎重になります。極端な場合には、不安障害やうつ病といったメンタルヘルスの問題と結びつくこともあります。
反対に神経症傾向の低い人は、情緒が安定していますが、鈍感な面もあるといえます。リスクを過小評価して、危険な行動に走りやすいといった可能性も考えられます。
外向性(Extraversion)
外向性–内向性という用語は、ユングのタイプ論に由来しています。
外向的な人は、外の世界に積極的に関わろうとし、活動的です。大勢でわいわい騒いだり、新しいものが好きです。ときに表面的なことに影響されすぎたり、行動が無謀になることがあるかもしれません。
内向的な人は、内気で、静かな生活を好み、行動は抑制的です。
どちらが優れているとか、適応的だというわけではなく、それぞれのタイプにぴったりした生活や人間関係をもてるのがいいのです。ユングによると、自我を固めて外界に適応しようとすること(外向性)も大事だし、自分の内面に目を向けて探求すること(内向性)にも重要な意味があります。その人なりの人生を歩みながら、内向性と外向性のバランスが取れていくのがいいのだとユングは考えました。
開放性(Openness to experience)
知性とか、知的好奇心、遊戯性とも訳されます。この傾向が強い人は、発想が独創的で、革新的なことを好みます。知的好奇心が豊かで、芸術などへの関心も強くもっています。極端な場合、発想が独創的すぎて、社会に収まりにくいことがあります。
反対に、この傾向が弱い人は、保守的で、慎重なタイプです。興味や関心はあまり広がりませんが、堅実に生きていくことができます。
協調性(Agreeableness)
同調性、調和性、愛着性とも訳されています。協調性が高い人は、人と関わることを好み、協力して行動することができます。共感的で、思いやりが強く、他人の世話をしたり、手助けする人たちです。協調性が高すぎると、他人に気を使いすぎたり、依存しすぎてしまうこともあります。
協調性が低い人は、他人に対してあまり親身にならず、自分のことを中心に考えがちです。敵意や自閉的な態度につながることもあります。
統制性(Conscientiousness)
自分の行動をどれくらい統制できるか、あるいは衝動的かということを反映する因子です。統制性の強い人は、目的意識が強く、最後まで根気をもって意思をつらぬくことができます。真面目で信頼できる人柄ですが、ときにこだわりが強くなりすぎるかもしれません。完全主義や強迫的な傾向とも関係しています。誠実性とも訳されています。
反対に衝動的な人は、そそっかしくて飽きっぽいという特徴をもっています。お金を計画的に使うのが苦手で、散財してしまいやすいでしょう。勉強や仕事への取り組みは、怠慢なところがあります。環境の変化が激しくて、素早い判断が求められる状況では、こうした人が生き延びるかもしれません。よく言えば、アクション映画のヒーローや狩人タイプです。
ビッグファイブを有名人や映画の登場人物で説明しているサイトをたまたま見つけたのですが、それによると「開放性」が高い例として挙げられているのはアルバート・アインシュタイン、統制性が高いのはロボコップ、協調性が高いのがフォレスト・ガンプ、そして低いのがドナルド・トランプでした。また、神経症傾向が高いのはウッディ・アレンで低いのがジェームズ・ボンド、外向的なのがバート・シンプソンで内向タイプがヨーダだそうです。なんだかわかるようなわからないような。
心理テストでパーソナリティを見る
5因子性格理論は、人をタイプにわける類型論ではなく「特性論」と呼ばれるものです。特性論は、パーソナリティをいくつかの特性(たとえば5つの因子)の集まりとして見ようとします。ある人は、「外向傾向と神経症傾向が強い」でしょうし、別の人は「統制性と内向性が強い」と言えるかもしれません。
こうしたパーソナリティ特徴をとらえるために、いくつかの心理尺度が開発されてきました。
日本で利用できる5因子正確理論を用いた心理テストは、主要五因子性格検査、FFPQなどいくつかありますが、かささぎ心理相談室では、NEO-PI-R性格検査を使っています。詳しくは「心理テスト」をご覧下さい。
「自分の性格傾向を知る」ということは、何も「自分はこういう人間だ」と決めつけるために行なうことではありません。心理テストの結果は、あくまでひとつの仮説です。その仮説を通して、自分自身についてより深く理解しようとすることで、これまで知らなかった自分と出会うことがあります。
自分を知ることで、抱えている問題を解消しやすくなったり、あるいは他人と上手につきあえるようになることも多いのです。
【参考文献】
ダニエル・ネトル『パーソナリティを科学する―特性5因子であなたがわかる』白揚社 、2009
サトウ タツヤ、渡邊 芳之『「モード性格」論―心理学のかしこい使い方』紀伊國屋書店 、2005