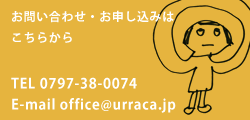FACE COVID−レジリエンス を高めるために
新型コロナウイルスと不安・ストレスへの対処(かささぎ通信)でも書きましたが、今日も新型コロナウイルスの話です。
RollingStone誌に「社会的不安を感じやすいのは自閉症の人々 不安を和らげるFACE COVID」という記事が掲載されていました。
新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で先の見通しが持てない今のような状況では、不安やストレスを抱くのは当然のことです。発達障害の特性を持った人は、とりわけ影響を受けやすいところがあります。
今日、明日にも出されることになりそうな非常事態宣言で、日常生活の変化は余儀なくされます。新型コロナウイルスがいつになったら落ち着くのか、収束するのかといったことは誰にもはっきりしたことは言えません。とても不確実な状況に皆が投げ出されています。
ノースカロライナ大学のフランクポーターグラハム児童発達機関の自閉症チームは、「不確実な時に自閉症の人たちを支援するということ」と題して、ウイルス拡大に不安な思いで生活している自閉症スペクトラム障害(ASD)の人たちとその支援者に向けた具体的な方法を7つにまとめて発信していて、それを川崎医療福祉大学が翻訳しています。この内容は、ASDの人や支援者のみならず、長期にわたって不安定な環境に置かれている子どもたち、そして大人たちにも有用な内容だと思いますのでご紹介します。
RollingStone
川崎医療福祉大学の「不確実な時に自閉症の人を支援するということ」も参照しながら、FACE COVID(ウイルスと向き合う)という対処法略について紹介します。ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)のRuss Harrisのアイデアとのことです。
FACE COVIDとは、次の9つの対処法略の頭文字から取った言葉だそうです。
- Focus on what you can control
- Acknowledge your thoughts and feelings
- Come back into your body
- Engage in what you are doing
- Commit to action
- Open up
- Values
- Identify resources
- Disinfect and distance
以下、連想やコメントを挟みつつ、読んでみますね。
Focus on what you can control あなたがコントロールできることは何?
Say to yourself “I can control what I am doing here and now.”
制御できる内容に焦点を当てる
「今ここで自分がやっていることをコントロールできる」と自分に言い聞かせてください。
心理学で「ローカス オブ コントロール(locus of control)」という概念があります。ローカス とは、場所や力の源という意味で、物理学などでは力点などとも訳されるようです。ですので、locus of controlとは「ものごとをコントロールする力の場所」といったことですね。
その場所が、自分の内部(つまり自身の努力や能力など)に置かれているか、それとも環境や運などの外部に置かれているか、ということです。
ジュリアン・ロッターというアメリカの心理学者によると、コントロール力が自分の内部にあって、人生を自らコントロールできていると感じている人のほうが、精神的に健康で、より幸福な人生を送ることができるのだそうです。
新型コロナウイルスによって不確実性が増している今だからこそ、「自分でコントロールできること」たとえば、感染予防や、睡眠や生活などの維持に焦点を当てることが大切になってきます。
そして、「コントロールできないこと」については、上手に手をはなすのも重要です。
よかったら、かささぎ通信の「コントロールすること、手をはなすこと」という記事もお読みください。
Acknowledge your thoughts and feelings 自分の考えや気持ちを認める
Silently and kindly acknowledge any thoughts and feelings
自分の考えや気持ちを認める
静かに、優しく、どんな考えや感情も認める
誰だって、「自分や大切な人が新型コロナウイルスに感染する(している)かもしれない」「この騒動で仕事を失うかもしれない」と考えるのは、怖いし、不安になるものです。
こういうとき、不安や恐怖を認めず(心理学用語で「否認」と言います)、「自分が感染するわけない」と、過度に楽天的になって危険な行動をしてしまうことがあります。
もちろん、適度な楽天さも必要ですが、行きすぎると、自分や周りの人の感染リスクを高めてしまうことになります。
「怖いよね、不安になるのも自然なことだよね」と、自らの気持ちにも目を向けてケアすることが必要です。
最近、臨床心理学で「セルフ・コンパッション」(self-compassion)という言葉をよく聞きます。セルフ・コンパッション とは、自分自身に向ける「優しさ」や「思いやり」「慈しみ」といったことです。
これも聞いたことがある人も多いと思われますが、「マインドフルネス」という考え方や方法を背景に、セルフ・コンパッション に注目されるようになってきたんですね。
クリスティーン・ネフの『セルフ・コンパッション―あるがままの自分を受け入れる』(金剛出版、2014年)によると、セルフ・コンパッションには、
- 自分への優しさ
- マインドフルネス
- 共通の人間性
という3つの要素があるのだそうです。
「自分への優しさ」とは、不安や恐れも含めて、自分を肯定的に認めてあげるということです。自らをいたわり、自分の長所や強みにもちゃんと目を向けるということも含まれています。
「マインドフルネス 」とは、自分の感情を偏りなく受け入れて、バランスの取れた見方をするということです。
「共通の人間性」とは、「こういう状況で不安や恐れを感じるのは誰しもあることだ」「誰だって完璧ではない」といったことを認めるということを意味しています。
自分の考えや感情を認めるためにも、セルフ・コンパッション が大切になってくると思います。
セルフ・コンパッション が高められると、不安感やストレスが減少し、困難な状況を乗り越えるための心の回復力(レジリエンス)や幸福感が強まると考えられています。
セルフ・コンパッション については、「心理学ワールド」の、
という記事が参考になります。セルフ・コンパッション を高めるための「慈悲の瞑想」についても触れられています。
関西大学の池見陽先生が考案した「観我フォーカシング」も、自身の思考や感情にありのままに目を向け、セルフ・コンパッションをもつための方法として適していると思います。
http://www.akira-ikemi.net/ewExternalFiles/Kanga%20FocusingPDF.pdf
Come back into your body いつもの身体の状態に戻る
Slowly stretch your arms or neck, shrug your shoulders
Take slow, deep breaths
いつもの身体の状態に戻る
腕や首をゆっくり伸ばしたり、肩をすくめたりします。
ゆっくり、深く深呼吸する
不安や恐怖、ストレスを抱えていると、身体が緊張したり、こわばったりします。ストレス状況に対して「闘争−逃走」反応を起こした身体は、心拍数が早くなり、呼吸は浅くなり、視野が狭まります。イライラして怒りっぽくなる、涙もろくなるといった感情的な反応も生じるかもしれません。
こうしたとき、少し時間をとって、自分の身体を観察してみましょう。
パット・オグデンらによる『トラウマと身体:センサリーモーター・サイコセラピー(SP)の理論と実践』(星和書店、2012年)という本を参考にしてみます。
不安や恐れに圧倒されているとき、身体は上で述べたような反応をしています。そして「思考」は「きっと自分も感染するに違いない」「仕事を失って路頭に迷うしかないだろう」「自分が悪かったから感染したんだ」といった否定的な考えでいっぱいになります。
そして、ネガティブな感情と思考と身体反応が、相互に刺激しあって、さらに自分を圧倒してしまうのです。
これは刺激や情報量が大きすぎる状態なので、うまく扱うことができません。
トラウマの身体的なセラピーの実践・研究をしているパット・オグデンは、こういうときは、「思考」「感情」「身体感覚」を分けて、情報量を制限することが大切だと言います。
たとえば身体感覚と動きにのみ注意を払い、感情とも思考とも違うものとして体験してみるのです。
胸が押し潰されそうな息苦しい感覚や、頭の重たい感覚「だけ」に注意を向けてみると、どんなことに気づくでしょうか?
「身体のこの感覚は、私に何を伝えているんだろう」
「この感じは、どうしたがっているんだろう」
と自分の身体感覚に尋ねてみてもいいでしょう。
「もっと深く呼吸をしたかったんだ」
「首を伸ばして、周りを見回したいんだ」といったことに気づくかもしれません。
あるいは、不快な身体感覚以外の身体の状況に、注意を向けてみることもできます。
息苦しさや重さに焦点を当てるかわりに、身体の「よい」感じや、「安全な」感じに気づいてみるのです。
辛いときにはどうしても、ネガティブな身体感覚だけに目がむきやすいものです。パニック障害の人が発作を起こすときも、呼吸のしづらさや不快感に注意が焦点づけられます。
でも、身体には「よい」あるいは「中立的」で、比較的「安全な」感覚をもっているところもあるのではないでしょうか?
そうした安全な感覚を増やすには、どうしたらいいでしょうか?
そのまま身体感覚の「安全さ」を感じ続けることもできるでしょうし、身体を伸ばしたり、動かしたりしてみることで、より「よい」「安全な」感覚が強まるかもしれません。
Engage in what you are doing 目の前のことに取り組む
Notice 5 things you can see, 3 things you can hear, 1 thing you can smell, and what you are doing
自分のやることに取り組む
あなたが見ることができる 5 つのこと、あなたが聞くことができる 3 つのこと、あなたが嗅ぐことができる 1 つのこと、そしてあなたがやっていることに注意を向ける
身体感覚も「今ここ」に戻ってくるための方法ですが、「五感で感じる目の前の現実」に注意と気づきを向けることも、「今ここにある」のを助けてくれます。
ゲシュタルト療法の「気づきの3つの領域」のエクササイズでは、「気づき」を、「思考」「からだ」「現実の世界」の3つの領域に分けて「今、何に気づいているか」に意識を向けます。
視覚では「今、何に気づいているか」、聴覚では「今、何に気づいているか」、触覚では? 嗅覚や味覚では?
こうした外部世界の現実に気づいていると、「ああなったらどうしよう」「自分はこういう(ダメな)人間だ」といった思考につかまりにくくなります。
また、「お皿を洗う」「歯を磨く」「ご飯を食べる」といった「今、していること」に、五感を通じて十分にコンタクトしながら取り組むことも大切です。
私たちは、ご飯を食べながら心配事を考えたりして、今ここから意識がどこかにさまよいがちです。
マインドフルネスでも強調されることですが、過去や未来、「もしも」の世界をさまようのではなく(これらはすべて「思考」「空想」の領域で起こっていることです)、「今ここ」に戻ってくることで、「ああなったらどうしよう」といった思考の反芻から抜け出せるのです。
Commit to action 行動リストを作ってみよう
What can you do this week to help yourself? Or others? Write it down in your schedule.
行動を明示する
今週は自分自身または他者を助けるために何ができますか?スケジュールに書き留めましょう。
このあたりは、認知行動療法の専門家が詳しいかもしれません。
自由に外出できなかったり、これまでやれていた活動が制限されるなかでも、自分や周りの人をサポートするためにできることはあるはずです。
そういったことをリストに書き出しておいたり、スケジュール帳に予定として入れておくことが、不安やストレスへの適切な対処行動・スキルとなります。
- 読みたい本や観たい映画をリストにしておく
- 近所を散歩をしたり、走ってみる
- 家の中でできる運動やストレッチ、ヨガなどをしてみる
- 家の片付けや庭仕事、日曜大工など(アメリカではペンキが売れているそうです)
- オンラインの英会話教室やグループなどに参加してみる
- 友人、知人、家族と、電話やオンラインでコンタクトしてみる
- 新しい知識やスキルを身に着ける機会にする
- 音楽を聴いたり、楽器を演奏してみる
- 絵を描いたり、写真を撮る
- アロマを炊いたり、ゆっくりお風呂に浸かってみる
- 新しい料理にチャレンジしてみる
他にもいろいろ挙げられるかもしれません。
ポイントは、「できるだけたくさん」「バランスよく」「無理なく」対処のための行動を用意しておくということです。
Open up 心を開く
Acknowledge that your feelings are normal and that it is okay to feel what you are feeling
心を開く
自分の気持ちが正常で、その気持ちを感じても大丈夫であることを認める。
これ、2番目の「自分の考えや気持ちを認める」と似てますね。というか同じなのかな。
先ほども述べたように、こうした危機的な状況においては誰だって不安や恐怖、孤立感、怒り、悲しみ、不満、罪悪感といった感情を抱くものです。
セルフ・コンパッション については上でも書いたので、ここでは「心を開く」ためにできそうなことを考えてみましょう。
マインドフル瞑想の時間をもつ
5分とか10分でも、ただ座って、今の自分が感じていることや、身体の感覚に「ありのままに」「判断せず」に目を向けてみてもいいかもしれません。
仏教の瞑想をもとにしてマインドフルネス ストレス低減法を考案したジョン・カバットジンは、
マインドフルネスとは、意図的に、今この瞬間に、価値判断することなく注意を向けること
と定義しています。
カバットジンの『マインドフルネスストレス低減法』(北大路書房、2007年)や『4枚組のCDで実践する マインドフルネス瞑想ガイド』(北大路書房、2013年)、『うつのためのマインドフルネス実践 慢性的な不幸感からの解放』(星和書店、2012年)などが参考になるかと思います。
インターネット上のリソースとしては、
NHKの
「マインドフルネス」とは?めい想の方法・効果と「呼吸のめい想」のやり方
や、関西学院大学の池埜聡先生のサイトに音声や動画のガイドがあります。
絵を描いて感情を表現する
かささぎ通信の「アマビエと鯰絵−民衆的想像力」という記事でも少し触れましたが、絵を描くということが、自分の気持ちに目を向けたり、感情を表現する手段となるかもしれません。
スケッチブック(落書き帳でもいいです)と好きな画材(クレヨン、色鉛筆、水彩絵具、なんでも)を用意して、「上手い下手は関係なく(自分を批判せずに)」「今ここで感じていることにしたがって」なんでも自由に描いてみてください。
- 五感で感じていること、気づいていることを表現してみる
- 身体で感じていること、気づいていることを表現してみる
- 頭の中の不安や恐れを描いてみる
- 気になる夢を表現してみる
といったことをしてみたらどうでしょうか?
なんだったら「アマビエ」の絵を描いてもいいんですよ(お守り効果があるかもしれません)。
あるいは、雑誌や写真、色紙、布切れなどを用意して「コラージュ」を作ってみることも、アートセラピーになります。
子どもにとっては、言葉で表現するより、絵などを通じた方が、自分の気持ちを表しやすいことがあります。大人にとっても、助けになることがあるんじゃないでしょうか。
落書き帳に、ただひたすら落書きするなんてのもいいですよ。
他にも、電話やオンライン通話などで友達やカウンセラーに今の気持ちを伝えてみたり、踊ったり歌ったり身体を動かしたり、ということを好む人もいるかと思います(他の人との距離に気をつけながら)。
Values 価値観
How do you want to treat yourself? Others? Values include love, humor, kindness, honesty…
価値感
あなたはどのように自分自身や他者をとらえたいですか?。価値観には、愛、ユーモア、優しさ、正直さなどがあります。
こういう大変なときだからこそ、「自分の人生においてもっとも大切なことはなにだろうか?」「私はどんなことに意味や価値を感じているだろうか?」といったことを自身に問いかけている人も多いのではないでしょうか。
恐れや心配、できなことではなく、「じゃあ、今、私は何を大切にして生きたいだろう」とふりかえってみることもときには必要です。
スティーブン・ヘイズらの『ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)をはじめる:セルフヘルプのためのワークブック』(星和書店、2010年)に、「価値」について扱った章がありました。
「価値」とは、「ゴール」や「目標」といった具体的なことではなく、人生の「方向」であり「選択」です。家を建てたり、結婚したり、学位をとるといったことは具体的な「ゴール」であり「目標」になりうるかもしれません。でも「価値」は、モノや資格のように所有することはできないんですね。
「西に向かう」ことを選択して歩き始めたからといって、「西」を手に入れることができるわけではないのと同じです。
「愛」や「絆」が自分の人生の価値だと思ったからといって、それらを「所有」できるわけではありません。
この本には、価値は「ゴール」や「感情」「結果」あるいは「未来」ではないと書かれています。
Identify resources リソース(資源)は何?
Identify ‘Who’ and ’Where’ to get help, assistance, and support
リソースを識別する
「誰に」、「どこで」助けてもらうか、補助してもらうか、支援を受けるかを決めておく
ZOOM飲み会、なんていうのが流行っているそうですが、こういった試みも「リソース」ですよね。
友人や家族、仕事仲間、医療や福祉の専門家、カウンセラーなど、サポートしてくれる人たちとのつながりを書き出しておくことで安心感を得られることもあります。
「社会的距離」を求められている今だからこそ、身近な人たちとのつながりが大切になってきます。
電話やメール、チャット、テレビ電話(って言わないか。ZOOMとかFacetimeとか)で人と関わる機会をもったり、手紙を描いてみるということも支えになるかもしれません。
新型コロナ拡大防止の鍵となるか 「遠隔診療」の可能性と課題を現役医師らに聞く
というニュースには、オンラインで診察を受けることのメリットやデメリットが書かれていました。
一月早く困難を体験した欧米ではカウンセラーや心理療法家もオンラインでのサポートをしているようですし、日本でも、取り組みは始まっています。
Disinfect and distance 消毒と距離
Wash your hands and practice social distancing
消毒と距離
手洗いと社会的な距離の練習を行う
これについては、いろいろなところで見聞きする機会があると思いますので詳しくは厚生労働省や自治体のサイトをご覧ください。
こういう状況になってあらためて思ったのは、カウンセリング場面で出会う方たちの「強迫症状」や「引きこもり」、「不安」「回避」といったいわゆる「症状」や「問題とみなされる行動」は、適応的な側面を含んでいるのだなあということです。
半年前の私たちが突然、今の状況にタイムスリップしてきたら、「みんながマスクをつけて人を避けて、ずっと手洗いしたり、消毒している」「学校にもくるなと言われている」とびっくりするんじゃないでしょうか。
こうした状況はしばらく続きそうですので、私たちも新しい対処法や生活・行動スタイルを身につけていく必要があります。
「完璧を自分(や他人)に求めず」「ほどよく」生活できるようになりたいと思います。
Youtubeに、FACE COVID – How To Respond Effectively To The Corona Crisisという動画がありました。