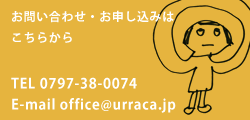アダルトチルドレンとインナーチャイルド──癒せなかった“子ども”と向き合う方法とは?

アダルトチルドレンとは?
アダルトチルドレン(AC)とは、本来「機能不全な家庭環境で育ったことによって、大人になってからも人間関係や感情の扱いに困難を感じやすい人」を指す言葉です。正式な診断名ではありませんが、多くの人が自分の“生きづらさ”を理解するための手がかりとして、この言葉に出会っています。
たとえば、
- 親の顔色を常にうかがっていた
- 家族の中で「しっかりした子」「聞き分けのいい子」としてふるまっていた
- 感情を表現することを許されなかった
- 親が不在、あるいは精神的に不安定だった
こうした経験を重ねた子どもは、「自分のままでは愛されない」「何かを我慢しなければ関係は続かない」といった思い込みを抱きやすくなります。
そして大人になったとき、親密な関係に不安を感じたり、他人に頼れなかったり、過剰に自分を責めてしまったりといったかたちで、生きづらさとして現れてくるのです。
アダルトチルドレンの苦しみは、子ども時代に安心して「子どもでいられなかった」経験に深く根ざしています。
その“傷ついた子ども”の存在は、大人になった今も、私たちの内側で助けを求めているかもしれません。
インナーチャイルドとは?
インナーチャイルドとは、「私たちの内側にいる、傷ついた子ども時代の自分」を意味する心理学的な概念です。
アメリカのセラピスト、ジョン・ブラッドショーやチャールズ・ウィットフィールドによって広まり、心の癒しやセルフケアの文脈で広く用いられるようになりました。ユング心理学にも、「内なる子ども」といった概念があります。
たとえば、
- 子どものころに甘えたかったのに甘えられなかった
- 悲しんだり怒ったりすると否定された
- 家族の中で「しっかり者」「聞き分けのいい子」としてふるまっていた
こうした経験を経て、「本当の気持ちを出すと嫌われる」「愛されるには役割を果たさなければならない」といった思い込みを、私たちは無意識のうちに心の奥深くにしまい込んでいきます。
それがやがて「インナーチャイルド(=傷ついた内なる子ども)」として残り、大人になってからの自己評価や人間関係に影響を与えることがあるのです。
※「インナーチャイルド」はアカデミックな臨床心理学の用語ではありません
この言葉はスピリチュアルの領域で広がった背景もあり、アカデミックな臨床心理学の中では正式な診断名や理論的枠組みとしては扱われていません。そのため、心理学の研究領域ではやや距離を取られている面もあります。
とはいえ、「インナーチャイルド」という発想そのものが示唆する心の動きは、以下のような心理療法・臨床理論と深く関係しています:
- 愛着理論(Bowlby, Ainsworth)
- 感情焦点化療法(Greenberg)
- ゲシュタルト療法(Perlsら)
- スキーマ療法(Young)における「傷ついた子どもモード」
- 内的家族システム療法(IFS)における「傷ついたパーツ」
これらは共通して、子ども時代に形成された未完了の感情や対人パターンが、現在の生きづらさにどのように影響しているかを丁寧に扱うアプローチです。
つまり「インナーチャイルド」という言葉は、学術的な枠組みとしては曖昧な部分もありますが、自分を理解し、優しく向き合うための“比喩的な入り口”としては非常に有効であると言えるでしょう。
変わりたいのに変われないとき、私たちは“怠けている”のではなく、“傷ついた子ども”がまだひとりぼっちでいるのかもしれません。
その子にそっと気づいてあげること。そこから本当の癒しが始まっていきます。
癒されない“子ども”が、大人の人間関係にどう影響するか
私たちは大人になっても、過去の記憶や感情の影響を完全に切り離して生きているわけではありません。
特に、子ども時代に抱えた「誰にもわかってもらえなかった」「気持ちを感じてもらえなかった」という体験は、心の深層に傷ついたままの“内なる子ども”=インナーチャイルドとして残り、気づかないうちに今の人間関係に影を落とします。
たとえばこんなふうに──
- 「人に頼ると迷惑をかける」と思って、つらくても一人で抱え込む
- 相手に嫌われないように合わせすぎて、自分の感情を後回しにする
- ちょっとした批判や無視に過剰に反応してしまい、深く傷つく
- 「ちゃんとしていないと愛されない」と、常に自分にプレッシャーをかけ続ける
- 親密な関係になりたいのに、近づくのが怖くて距離をとってしまう
これらはすべて、かつて「そうするしかなかった」子どもの防衛反応が、大人になっても自動的に繰り返されているパターンと見ることができます。
本当はもう過ぎたはずの状況なのに、心の中の“癒されていない子ども”が、「また傷つくかもしれない」「今度こそ見捨てられるかも」と過剰に反応してしまうのです。
そしてこのような無意識の反応は、恋愛や職場、友人関係といったあらゆる対人場面で繰り返され、「また同じことをしてしまった」「人といると疲れる」という“生きづらさ”につながります。
こうした反応は、「性格」や「甘え」ではなく、かつての環境に適応するために身につけた知恵の名残です。
それゆえに、頭でわかっていても「やめられない」「変えられない」と感じるのは自然なことです。
癒されていないインナーチャイルドが私たちの行動を握っているとき、それは「変わる」よりも、「気づいて、安心させてあげる」ことのほうが先なのかもしれません。
インナーチャイルドと向き合う方法
「過去はもう終わったこと」と頭ではわかっていても、心のどこかで、まだ“あのときの自分”が動けずにいる感覚。
それが、インナーチャイルドが今もあなたの内側に存在しているというサインかもしれません。
インナーチャイルドと向き合う方法には、セルフワークと心理療法(カウンセリング)の両方があります。
セルフワークのいくつかの例:
- 傷ついた子ども時代の自分に手紙を書く
- 安心感の象徴としてのぬいぐるみやクッションと対話する
- 当時の自分をイメージで再現し、やさしく声をかける
- 子どもだった頃にしたかったことを今の自分が“親代わり”になってやってあげる
これらのワークに共通するのは、「今の自分」が「過去の自分」と関わり直すこと。
置き去りになっていた感情やニーズに“今ここ”で気づいてあげることが、癒しの第一歩となります。
ゲシュタルト療法の視点から:癒しとは「適応の知恵」との対話
ゲシュタルト療法では、子ども時代の反応を「創造的調整(creative adjustment)」と捉えます。
たとえば、
- 怒りを抑えて「いい子」でいた
- 自分の気持ちを後回しにして家族に合わせていた
- 感情を感じないようにしてやり過ごしていた
これらは、当時の環境の中で自分を守るために編み出した知恵であり、生き抜くための柔軟な対応だったのです。
しかし、その「適応」は大人になった今も、自動的に繰り返されていることがあります。
ゲシュタルトでは、こうしたパターンを「未完了の仕事(unfinished business)」と呼び、カウンセリングの場で再び“今ここ”に持ち出し、完了へと向かう対話や体験を大切にします。
たとえば、当時は言えなかった「いやだった」「寂しかった」「わかってほしかった」という気持ちを、今の自分が安全な場で表現できたとき、心の中に残っていた未完了のエネルギーが自然とほどけていくのです。
心理療法・カウンセリングという「新しい関係の体験」
ひとりでセルフワークに取り組むことが難しい場合は、心理士との対話という関係性のなかで、安全にインナーチャイルドと向き合っていくことも可能です。
とくに、ゲシュタルト療法や感情焦点化療法(EFT)、内的家族システム療法(IFS)などは、
“過去の傷ついた部分”を今の関係性のなかで癒していくアプローチとして有効です。
「自分はもう大人だから、癒されなくても我慢すればいい」――
そうやって耐えてきた心に、今こそ「もう一度出会い直す」機会を届けてみませんか?
神戸でアダルトチルドレンやインナーチャイルドに対応したカウンセリングを受けるには
アダルトチルドレンやインナーチャイルドのテーマに取り組むうえで、「ひとりで抱え込まず、安心できる場所で話すこと」はとても大きな支えになります。
神戸・芦屋エリアには、こうした心の深いテーマに丁寧に対応できる臨床心理士・公認心理師によるカウンセリングルームがあります。
たとえば「かささぎ心理相談室」では、アダルトチルドレンの生きづらさや、インナーチャイルドの癒しに焦点を当てた心理療法(ゲシュタルト療法・感情焦点化療法・IFSなど)を行っています。
初回の面接では、今感じている悩みや違和感、話せる範囲のことから自由にお話しいただけます。
「まとまっていなくてもいい」「何を話したらいいかわからなくてもいい」──そうした気持ちのままで大丈夫です。
また、オンラインでのカウンセリングにも対応しているため、神戸周辺以外にお住まいの方や、外出に不安がある方でもご利用いただけます。
心の中にずっと残っていた声に、そっと耳を傾ける時間を、ぜひ自分自身に贈ってみてください。
よくある質問(Q&A)
Q. インナーチャイルドを癒すって、ちょっとスピリチュアルな感じがして抵抗があります。
A.
たしかに「インナーチャイルド」という言葉にはスピリチュアルなイメージがつきやすい面がありますが、
ここで扱っているのは“心の中に残っている傷ついた子ども時代の記憶や感情”を心理的に理解し、ケアしていくプロセスです。
これは、愛着理論や感情焦点化療法(EFT)、ゲシュタルト療法などの心理臨床の理論と深くつながっているアプローチであり、「自分に優しくなる力」を育てていく、地に足のついた取り組みです。
Q. 過去を掘り返すことに意味はあるのでしょうか?つらくなるのでは?
A.
「過去は忘れたほうがいい」と思う方も多いですが、未完了の感情が今の自分に影響を与えていることも少なくありません。
ゲシュタルト療法では、過去を「掘り返す」のではなく、“今ここ”での感じ方として丁寧に扱っていきます。
つらい記憶を無理に思い出すのではなく、「今この瞬間に、何が起きているのか」に注目することで、自分を苦しめていた反応の仕組みに気づくことができます。
Q. 自分の中の“子ども”と向き合うなんて、なんだか恥ずかしいです…
A.
そう感じるのはとても自然なことです。でも、多くの人が思いがけず「安心した」「涙が出た」と感じるのが、“わかってほしかった自分”に出会えたときです。
向き合うと言っても、無理に演じたり、子どもっぽくふるまったりする必要はありません。
「今まで気づいてあげられなかった気持ちに、少しだけ目を向けてみる」──それだけでも、癒しのプロセスは静かに始まっていきます。
Q. カウンセリングでは、どんなことをするのですか?
A.
初回の面接では、話しやすいことからゆっくりお聞きします。
必要があれば、家庭環境や子ども時代のことにも触れますが、話したくないことを無理に聞くことはありません。
カウンセリングでは、「今この場でどんな感情や身体感覚が起きているか」に注目しながら、
心の奥に残っている“未完了の感情”にやさしく気づき、表現していくことを大切にしています。
Q. 神戸近郊に住んでいないのですが、相談は可能ですか?
A.
はい。オンラインでのカウンセリングにも対応しています。
ビデオ通話を使って、全国どこからでも安心してご相談いただけます。
対面でのご相談が難しい方や、HSP・AC傾向のある方にとっても、自分のペースで話せるオンラインの環境はとても好評です。
Q. 子どもの頃のことを何十年も放置してきましたが、今からでも癒せますか?
A.
もちろんです。心は時間が経っても癒しを待ち続けています。
むしろ、「今の自分なら、あの頃の自分にやさしく関われる」「ようやく向き合える準備ができた」と感じられることも少なくありません。
年齢やタイミングに関係なく、“今のあなた”にしかできない関わり方があります。遅すぎることはありません。
Q. 自分の気持ちがよくわからず、感情が出てこないのですが…
A.
アダルトチルドレンや心の傷を抱えた方によくある反応です。
長年、感情を抑え込んできた人ほど、「何を感じているのかわからない」「感じないようにしている」となることがあります。
無理に感情を“出そう”とする必要はありません。
カウンセリングでは、身体感覚や沈黙も大切な“感情の入り口”として扱います。ゆっくりと、感情に触れる準備ができるところから始めていきましょう。
Q. 家族への怒りが止まらず、自分が嫌になります。
A.
その怒りは、「わかってもらえなかった」「大切にされなかった」自分の感情がようやく表に出てきた証かもしれません。
怒りは本来、自己を守るための大切なエネルギー。長く抑えていたぶんだけ、激しくなることもあります。
「こんな自分ではいけない」と否定するのではなく、「そのくらい傷ついていたのだ」と理解することが、怒りを癒しに変える最初のステップです。