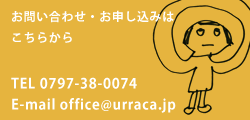神戸のスクールカウンセラーが語る子供が「学校に行きたくない」理由と親ができること
はじめに:20年のスクールカウンセラー経験から伝えたいこと
こんにちは。神戸市でスクールカウンセラー(SC)として20年以上、小学校、中学校、高校と様々な現場で子どもたち、保護者の方々、そして先生方と合ってきました。これまでに「学校に行きたくない」と悩む多くの児童生徒に出会いました。
この問題は、決して特別なことではありません。子どもたちの数だけ理由があり、その背景には様々な思いが隠されています。そして、何よりも保護者の皆さんが「どうすればいいのだろう」と不安を抱えていることを痛いほど理解しています。
この記事では、スクールカウンセラーとして働いてきた経験から、「学校に行きたくない」という子どもたちの複雑な心境とその理由を考えてみます。そして、保護者の皆さんがお子さんを理解し、具体的な一歩を踏み出すための実践的なアドバイスを、神戸の地域性も踏まえながらお伝えできればと思います。
「学校に行きたくない」は“甘え”ではない:背景にある子どものSOS
「学校に行きたくない」という言葉を聞くと、「甘えているのでは?」「みんなは行けているのに」と感じてしまうかもしれません。しかし、これは決して甘えではありません。子どもたちが発するSOSだと受け止めることが、問題解決の第一歩です。
多くの場合、子どもたちは自分がなぜ学校に行きたくないのか、うまく言葉にできないものです。体調不良を訴えたり、無気力になったり、あるいは親に反抗的な態度を取ったりすることもあります。これらはすべて、子どもが抱える心の葛藤やストレスの表れです。
2016年に施行された「教育機会確保法」は、学校以外の多様な学びの場や、休養の必要性を明確に示しています。これは、子どもたちが学校に「行かなければならない」というプレッシャーから解放され、自分に合ったペースで成長できる環境を選ぶ権利があることを意味しています。
子どもが「学校に行きたくない」と感じる多様な理由:年代別の傾向と神戸の事例から
子どもが学校に行きたくないと感じる理由は多岐にわたります。私の経験から、主な理由と年代別の傾向、そして神戸の学校現場で見られた具体的なケースを交えながら解説します。
1. 自分でも理由がわからない、言葉にできない不調
子どもたちは、大人以上に自分の感情や体調の変化を言語化するのが苦手です。特に小学校低学年の子どもの場合、朝の頭痛や腹痛、夜の不眠など、身体的な不調を訴える形で心のSOSを発することがよくあります。神戸市内の小学校でも、新しい環境への適応に時間がかかり、漠然とした不安から体調を崩すケースを多く見てきました。
2. 心身の疲弊と集団生活のストレス
いじめや学業不振といった明確な理由がなくても、集団生活そのものが大きなストレスになることがあります。特に敏感な子どもは、教室の喧騒、先生の叱責、友だちとの些細な摩擦など、日常的な刺激に心身が疲弊してしまうことがあります。私が見てきた中には、クラスでの立ち位置や周囲の評価を気にしすぎてしまい、毎日学校に行くこと自体が重荷になっている中学生もいました。
3. 学業不振と進路への不安
学業の遅れや苦手意識は、子どもにとって大きな自信喪失につながります。特に中学校、高校と進むにつれて、テストの点数や成績、そして将来の進路への不安が募り、学校から足が遠のくケースが増えます。神戸市内の高校でも、大学受験を意識し始める時期に、成績へのプレッシャーから登校しぶりを見せる生徒が少なくありませんでした。
4. 人間関係の悩み:いじめだけではない複雑な問題
いじめはもちろん深刻な問題ですが、それ以外にも人間関係の悩みは尽きません。友人とのすれ違い、グループに属せない孤独感、部活動での人間関係など、子どもにとって友だち関係は学校生活の大きなウェイトを占めます。私が経験したケースでは、親友との些細な喧嘩をきっかけに、学校に行くことが辛くなった小学校高学年の子どももいました。
5. 家庭環境と子どもの心
家庭内の問題が、子どもの登校に影響を与えることも少なくありません。親子関係の不和、家族間のトラブル、あるいは過度な期待やプレッシャーなど、家庭が子どもにとって安心できる場所でなくなると、学校に居場所を見つけられなくなることがあります。
6. いじめによる心身の苦痛
「いじめ」は、子どもが学校に行きたくなくなる最も深刻な理由の一つです。直接的な暴力だけでなく、言葉の暴力、無視、仲間外れ、SNSなどでの誹謗中傷などもいじめに該当します。いじめを受けている子どもは、心身に大きなダメージを受け、自己肯定感が低下し、学校が「安全な場所」ではなくなってしまいます。学校や家庭に相談できないまま、一人で苦しみを抱え込んでしまうケースも少なくありません。神戸市内でも、いじめの相談は絶えず寄せられており、早期発見と適切な対応が何よりも重要です。
7. 発達特性(ASD、ADHD、LDなど)による学校生活の困難
近年、発達障害の特性を持つ子どもたちが学校生活で直面する困難が注目されています。
- ASD(自閉スペクトラム症): 他者とのコミュニケーションや社会性の困難、特定の物事への強いこだわり、感覚過敏などにより、集団生活に馴染みにくさを感じることがあります。例えば、教室の騒音や、曖昧な指示が理解しにくいことなどがストレスとなり、登校を渋る原因となることがあります。
- ADHD(注意欠陥・多動性障害): 不注意、多動性、衝動性といった特性により、授業に集中できなかったり、忘れ物が多かったり、衝動的な言動でトラブルになったりすることがあります。これらの経験が積み重なることで、自己肯定感が低下し、学校に行くことへの抵抗感が生じることがあります。
- LD(学習障害): 聞く、話す、読む、書く、計算するといった特定の学習分野に著しい困難を抱えることがあります。他の子と同じように学習できないことに劣等感を抱いたり、先生から理解されないと感じたりすることで、学校に行くのが嫌になることがあります。
これらの発達特性を持つ子どもたちは、学校の画一的な教育環境では、本来持っている能力を発揮しにくく、誤解されたり、適切な支援を受けられなかったりすることがあります。早期に特性を理解し、個別の配慮や支援を提供することが、彼らが安心して学校生活を送る上で不可欠です。神戸市内の学校でも、発達特性を持つ子どもたちへの理解と支援の必要性は高まっています。
年代別に見る「学校に行きたくない」傾向と神戸の地域差
長年の経験から、年代によって「学校に行きたくない」理由や子どもの反応に特徴があると感じています。さらに、神戸という地域性も、子どもたちの悩みに影響を与えていると感じています。
小学生:環境変化と自己表現の難しさ
- 低学年: 幼稚園や保育園からの環境の変化、集団生活への不慣れからくる戸惑いが多いです。「小1プロブレム」として知られる現象も、この時期に顕著です。言葉で気持ちを表現するのが苦手なため、癇癪や体調不良として現れることが多いでしょう。神戸市内の小学校では、特に園からの移行期に親御さんから相談を受けることが多くありました。
- 高学年: 自己肯定感の形成と同時に、周囲との比較から劣等感を抱きやすくなります。友人関係が密になり、トラブルが深刻化する傾向があります。また、集団登校時の問題や、特定の友人との関係性で悩むケースも増えます。この時期から、軽度の発達特性が見られる子どもの場合、集団でのルール理解やコミュニケーションの難しさから、学校に馴染めないと感じ始めることもあります。
中学生:思春期の葛藤と自立への揺れ動き
- 学業へのプレッシャー: 勉強が本格化し、成績や内申点への意識が高まります。進路への不安も加わり、学業不振が登校しぶりの大きな要因となることがあります。
- 親への反発と秘密: 親よりも友人を重視し、親に秘密を抱えがちになります。部屋にこもったり、スマホやゲームに没頭したりすることで、現実から目を背けようとすることもあります。
- 起立性調節障害: 思春期に多く見られる疾患で、朝起きられない、めまい、倦怠感などの身体症状が伴います。怠けていると誤解されやすいですが、医療的なサポートが必要なケースも少なくありません。神戸の相談室でも、この症状を訴える中学生の保護者からの相談が後を絶ちません。
- 発達特性の顕在化: 小学校では目立たなかった発達特性が、学習内容の高度化や人間関係の複雑化によって顕在化し、本人が学校生活で困難を感じやすくなる時期です。特にADHDの特性がある場合、課題の提出や時間管理の困難さが成績に影響し、自信を失うことがあります。また、ASDの特性がある場合、友人関係の複雑さに疲れ、孤立感を感じやすくなることもあります。
高校生:複雑化する理由と将来への不安
- 進路・学業の重圧: 義務教育ではないため、単位取得や進級のプレッシャーが大きく、留年への不安から休みにくい状況が生まれます。将来の進路選択という、一人で抱えきれない問題に直面する時期でもあります。
- 理由の複雑化: 無気力・不安、生活リズムの乱れ、友人関係、遊びや非行など、様々な要因が複雑に絡み合い、登校しない理由が多様化します。心の不調を放置すると、長期化や重症化のリスクも高まります。
- いじめの多様化と複雑化: SNSなどインターネットを介したいじめが増え、より発見が難しく、陰湿化する傾向にあります。物理的な接触がなくても、精神的なダメージは非常に大きいものです。
- 発達特性と将来への不安: 発達特性を抱える生徒は、高校卒業後の進路選択において、より大きな不安を感じることがあります。自身の特性とどう向き合い、社会で生きていくかという課題に直面し、登校へのモチベーションを失うことがあります。
神戸の地域性から見る子どもの悩み
神戸市内の学校でカウンセリングをしてきて感じるのは、立地による子どもの悩みや親の関わり方の傾向の違いです。山手の地域の学校に通う子どもたちは、幼少期から教育熱心な家庭が多く、高学力層が集まる傾向にあります。そのため、「学校に行きたくない」という悩みも、成績不振や進路への過度なプレッシャー、あるいは友人関係における競争意識が背景にあるケースが多いようです。親御さん自身も高学歴であるため、子どもの将来への期待が高く、結果として子どもがプレッシャーを感じやすい状況があります。カウンセリングでは、そうした親子のコミュニケーションのあり方や、子どもの自己肯定感を育む支援が重要になります。また、発達特性を持つお子さんの場合、周囲のレベルが高いがゆえに、学習の遅れや集団行動の難しさがより顕著に感じられ、本人の劣等感が深まるケースも見受けられます。
阪神沿線沿いの地域では、多様な家庭環境の子どもたちが集まります。そのため、悩みも多岐にわたり、家庭環境の課題(親子関係の不和、経済的な問題など)が学校での問題行動や不登校に繋がっているケースも少なくありません。また、友人関係もより複雑で、コミュニケーション能力の課題や、集団の中で居場所を見つけられないという悩みを抱える子どももいます。カウンセリングでは、子ども自身の自己表現の支援に加え、家庭への具体的なサポートや、地域との連携がより一層求められることがあります。いじめの問題も、多様な背景を持つ子どもたちが集まるがゆえに、価値観の相違から生じやすい傾向があります。
もちろん、これはあくまで傾向であり、個々の子どもや家庭の状況は様々です。しかし、地域の特性を理解することは、子どもの悩みの背景を深く読み解き、適切な支援に繋げる上で非常に役立ちます。
「学校に行きたくない」と言われたら?親ができる具体的な対応
お子さんから「学校に行きたくない」と聞かされた時、どう対応すれば良いのか、具体的なステップと心構えをお伝えします。
1. まずは「子どもの話を聞く」こと:共感と受容が大切
お子さんが「学校に行きたくない」と言い出したら、まず焦らずに、お子さんの話をじっくりと聞く姿勢を大切にしてください。「なぜ行きたくないの?」と理由を問い詰めるのではなく、「そうか、学校に行きたくないんだね」と、まずはその気持ちを共感し、受け入れることから始めましょう。
私がカウンセリングで大切にしているのは、お子さんが安心して話せる「安全基地」となることです。親が味方であると感じられれば、子どもは少しずつ心の内を語り始めるでしょう。たとえ理由が曖牲模糊でも、それを否定せず、「辛いんだね」「苦しいんだね」と、感情に寄り添うことが重要です。
2. 「休む」という選択肢を柔軟に考える
「休んだら、もっと行けなくなるのでは?」と不安に感じるかもしれませんが、無理をして登校させることで、かえって心身の不調が悪化するケースも少なくありません。時には、休むことが前向きな選択となりえます。
「今日は休んでゆっくりしようか」「午後から行ってみる?」など、選択肢を提示し、子どもの意思を尊重する姿勢を見せましょう。休むことで心身が回復し、「また行ってみようかな」と意欲が湧いてくることもあります。
3. 体調の変化に注意し、必要であれば医療機関へ
朝の頭痛や腹痛、吐き気など、学校に行く前や登校中に身体症状を訴える場合は、心身症や起立性調節障害などの可能性も考えられます。自己判断せず、まずはかかりつけの小児科や心療内科を受診し、専門医の診断を仰ぎましょう。私も、医師と連携しながら、お子さんの状態を把握し、適切なサポートを行うことがよくあります。
4. 学校との連携を密にする:担任の先生やスクールカウンセラーへ相談
お子さんの状況を担任の先生や学校のスクールカウンセラーに早めに伝え、連携を図りましょう。学校側も、お子さんの状況を把握することで、学習面や友人関係での配慮、あるいは別室登校などの支援を検討してくれます。**いじめが疑われる場合は、迅速に学校に報告し、具体的な対応を求めましょう。また、発達特性が疑われる場合は、学校と連携して専門機関での検査や診断を検討し、個別の教育支援計画の作成を依頼することも重要です。**私も、学校内で保護者の方と連携を取りながら、お子さんの学校生活をサポートしてきました。
5. 多様な学びの選択肢を視野に入れる
学校への登校が難しい場合でも、学びの機会は多様に存在します。
- 通信制高校・サポート校: 中学生・高校生であれば、通信制高校やサポート校という選択肢があります。自分のペースで学習を進められ、進路相談なども手厚い場所が多いです。神戸市内にも複数の通信制高校やサポート校があり、私自身も多くの生徒を紹介してきました。
- フリースクール: 学校以外の居場所として、フリースクールも有効な選択肢です。学習支援だけでなく、様々な体験活動や人との交流を通じて、お子さんが自分らしく過ごせる場を提供しています。
- 自宅学習: 家庭での学習をサポートする教材やオンライン授業なども活用できます。
- 適応指導教室(教育支援センターなど): 各自治体に設置されていることが多く、学校への復帰を目指す子どもたちが通う場所です。学習支援や居場所提供、カウンセリングなどが行われます。神戸市にも同様の施設があります。
おわりに:一人で抱え込まず、専門家を頼る勇気を
「学校に行きたくない」という問題は、保護者の方だけで抱え込むにはあまりにも大きなものです。私自身、20年間スクールカウンセラーとして多くのケースを見てきましたが、一人で悩みを抱え続けることで、親子関係が悪化したり、お子さんの問題が長期化するケースも少なくありません。
神戸市には、経験豊富なスクールカウンセラーや、臨床心理士、精神保健福祉士、医療機関など、子どもの心と成長を支える専門家が数多くいます。また、教育委員会や地域の相談機関も、不登校に関する相談を受け付けています。
どうか、一人で抱え込まず、専門家の力を借りる勇気を持ってください。あなたの不安や悩みを話すことで、きっと解決の糸口が見つかるはずです。お子さんの「学校に行きたくない」という言葉の裏には、成長しようとする新たな一歩が隠されていることもあります。その一歩を、一緒に見守り、支えていきましょう。