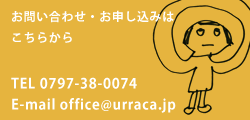職業としての心理臨床家
芦屋の駅のそばに新しく書店ができたので立ち寄ってみました。
「未来屋書店」という、本と雑貨が置いてある店です。
ビブリオセラピー(読書療法)
「Bibliotherapy あなたを癒す70の処方箋」というコーナーがあって、薬局でもらうような袋の中にそれぞれの「症状」に効く文庫本がセレクトされているというもので、なかなか面白かったんです。
たとえば、
「大人になりたくない」
「最近笑ってない」
「優しくなれない」
といった「症状」です。
何冊か、袋の中身をのぞいてみて、「なるほど、この本か」と思ったり、意外に感じたり。
ほかにも、「誕生日」や「地域」「苗字」などで選ばれた本(田中さんに関する本、といった感じのブックカバーがかけられている)が並んでいて楽しかったです。普段は読まない本に出会えそうな、いい工夫だと思いました。
芦屋駅あたりにお立ち寄りの際に、よかったらのぞいてみてください(と地域振興のために宣伝してみる)。
職業としての心理臨床家
手に取って買ったのは、村上春樹の『職業としての小説家』。
紀伊國屋書店がアマゾンに対抗して買い占めた、というニュースが最近流れていましたが(これも書店の試みのひとつですね)、違う本屋さんにもちゃんと置いてありました。
午前中、ちょっと時間があったので、お弁当をもって芦屋川の上流の「高座の滝」までいって、そこでしばらく読書をしました。
気持ちのいい滝のそばで本を読みながら、「職業としての心理臨床家」ということについて、少し考えてみました。
ちょうど何日か前に「公認心理師」という国家資格が国会で可決成立したばかりです。
それにそういえば今日は神戸で「心理臨床学会」が開催されているのでした(すっかり忘れてた)。
「心理臨床家」という呼び方は、どうも肩に力が入ってるような気もして、自分で名乗るには少し恥ずかしいのですが、この仕事をしてそれなりに長くなってきたので、(小声で)そう言ってもいいんじゃないかなとは思います。「カウンセラーです」と言うことの方が多いけれども。
『職業としての小説家』を読んでいると、小説家と心理臨床家は、どこか似ているところがあるんじゃないか、と思わされます(小説なんて書いたことないですが)。
あるいは、教師や農家や僧侶といった職業の人たちも、この本を読んで同じように、「小説家と教師はどこか似たところがある」などと思うのかもしれません。優れた文章を読むと、それだけ「自分のことと似ている」と感じるものなのかもしれない。
物語のあるところ
でも、この本の最後の章(「物語のあるところ・河合隼雄先生の思い出」)で、村上春樹さんはこんなことを書いていました。
物語というのはつまり人の魂の奥底にあるものです。人の魂の奥底にあるべきものです。それは魂のいちばん深いところにあるからこそ、人と人とを根元でつなぎ合わせられるものなのです。僕は小説を書くことによって、日常的にその場所に降りていくことになります。河合先生は臨床家としてクライアントと向き合うことによって、日常的にそこに降りていくことになります。
だとすると、小説家と心理臨床家が似ているということも、あながち間違いではないのかもしれません。
村上さんが言うには「小説なんて、書こうと思えばほとんど誰にだって書ける」のだそうです(うーん、そうなのかな)。
カウンセリングも、言ってみれば「話を聞くなんて、ほとんど誰にだってできる」ことが仕事になっています。「書く」と「聞く」の違いはあっても、「誰にだってできる」ことをつきつめる、という点では似ているんでしょう。
面白かったのは、小説というジャンルを「誰でも気が向けば簡単に参入できるプロレス・リングのようなもの」と喩えていたところです。
「しかしリングに上がるのは簡単でも、そこに長く留まり続けるのは簡単ではありません」
と村上さんは書きます。
小説を書き続けて、生活していくこと、生き残っていくことは至難の業で、「何か特別なもの」が必要になってくると言うのです。それはある種の「資格」のようなものです。もともとそれが備わっている人もいれば、後天的に苦労して身につける人もいる。それは公の資格として免状をもらうことができない種類のものですが、その言葉にしがたい「資格」みたいなものがなければ、小説家であり続けることは困難なようです。
カウンセラーの「資格」
ここで再びカウンセラーや心理臨床家としての「資格」についても考えてみたくなります。
カウンセリングやセラピーの理論や方法はあちこちで学ぶことができます。なんたって、カウンセリングを受けたい人より、カウンセラーになりたい人の方が多いんじゃないかって言われる時代です。
「カウンセラーするよりも、カウンセリングスクールした方がお金になるよ」なんて言う人もいる。
でもカウンセラーであり続けて、生活したり、生き残っていくことは確かに至難の業で、「資格」とでもいうような何かが必要なのかもしれません。
でもそれはたぶん、「臨床心理士」や「公認心理師」といった目に見える資格とは違うんじゃないでしょうか。国家資格ができたことも確かに大事で、よかったなとは思うけど。
じゃあ、いったいその「資格」ってなんだろう。
なんてことを考えていると、はたして自分にその「資格」があるのかないのか、だんだん不安になってきます。「この人には資格がある」「ない」といった固定されたものではなくて、あるいはそれは流動的な状態なのかもしれません。
クライアントとともに「深いところに降りていく」なかで、その「資格」は何度も試されることになるでしょうし、心理臨床家としてそこに「ある」か「ない」かもまた繰り返し問われることになるのだと思います。
『職業としての小説家』を読んでいると、勝手に投影しているだけですが、他にも「カウンセラーと似ているのかも」と感じられる文章がいくつも見つかります。
たとえばこういうところ。
小説を書くというのは、とにかく実に効率の悪い作業なのです。それは「たとえば」を繰り返す作業です。ひとつの個人的なテーマがここにあります。小説家はそれを別の文脈に置き換えます。「それはね、たとえばこういうことなのですよ」という話をします。(中略)というのがどこまでも延々と続いていくわけです。限りのないパラフレーズの連鎖です。
カウンセリングもまた、回りくどくて、効率の良くない作業です。
賢い人なら、「話はわかった皆まで言うな」と話をさえぎって、問題をぱっぱと解決してしまうのかもしれません。
けれども回りくどいところにある個人的なテーマに、「たとえばこうかな」「たとえばああかもしれない」と何度も何度も触れながら、一歩ずつ降りていくことでしか現れてこない「物語」もあるんじゃないでしょうか。
最後にもう一度、「資格」について書かれているところを引用します。
じゃあ、その資格があるかどうか、それを見分けるのはどうすればいいか? 答えはただひとつ、実際に水に放り込んでみて、浮かぶか沈むかで見定めるしかありません。乱暴な言い方ですが、まあ人生というのは本来そういう風にできているみたいです。
小説家とカウンセラーの違うところは、われわれは一人仕事ではなくてクライアントの旅に同行するのが務めなので、いっしょにおぼれてしまうわけにはいかないということです。片手か、あるいはロープの一本でも、岸につなぎとめて、クライエントさんとともになんとか生きのびるようにするのが勤めです。
ふと思い出したのが、ずいぶん前に読んだ『精神療法家として生き残ること』(ニナ・コルタート)という本です。「職業としての精神療法家・精神分析家」というタイトルにしてもよいような本だったと記憶しています。精神療法家(心理臨床家と同じような意味合いです)になることが、いかに苦しくて、またいかに楽しいか、といったことが彼女の人生と重ね合わせて語られていました。
—
プロレスのたとえがあったので、これまた連想したのがミッキー・ローク主演の『レスラー』という映画。「職業としてのプロレスラー」の生き様が描かれたいい映画でした。
***
2019年9月24日追記:芦屋の未来屋書店は、残念ながら今年、閉店してしまいました。「町の本屋さん」はamazonに押されて、だんだん厳しくなってきているのかもしれません。「カウンセラーの資格」についていえば、今年、「公認心理師」という国家資格が誕生し、私たち、かささぎ心理相談室のカウンセラーも「公認心理師」という「資格」を掲げて仕事をすることになりました。「臨床心理士」としても引き続き、努めていきます。かささぎ心理相談室が開室してから、もうじき10年になります。これまではいちおう、カウンセラーとして「生きて」これたと言うこともできそうです(個々のセッションの中では、カウンセラーとして生きていることもあれば、そうできない瞬間もあったと思います)。なんとか溺れずに、泳ぎ続けては来たのかな。10年後、カウンセラー、あるいは心理臨床家として、どんな風に生きているのかはまだわかりません。心理臨床家として生きることが、どういうことなのかも、わかったような、わからないような気がします。それは、「たとえばそれは、こういうことなのかな」といった問いかけと、クライエントやカウンセラー仲間との対話を通じて、少しずつ積み重ねたり、崩してみたり、を続けていくしかないことなのでしょう。
ニナ・コルタートの『精神療法家として生き残ること』は、再販されたらしいので、また読み返してみたいと思っています。