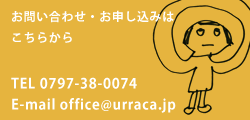焚火と瞑想

11月30日に第一回公認心理師国家試験の合格発表があり、なんとか無事に合格することができました。
とりあえずホッとしたので、何度か行ったことのある滋賀県のキャンプ場に一人で一泊してきました(試験に落っこちたときの引きこもり先と思っていたんです)。
オーナーさんが森を切り開いて作ったキャンプ場で、それぞれのサイトに直火で火を焚くことができる石造りのファイヤーピットが備え付けられています。
電車移動のソロキャンプなので、できるだけ身軽にしたいところです。
テントは置いていくことにして、持ち物は寝袋と敷物と小さなツェルトと食器くらいにしました。
日が暮れて、焚火の炎を一人で眺めていると、日常の気がかりや悩みごとも、少しのあいだ横に置いておくことができます。
私たちは常日頃、
「こうなったらどうしよう」
「あの人は自分のことをこう思ってるんじゃないか」
「自分はダメな(あるいはよくない)人間に違いない」
といったことをぐるぐると考えては自分を損なったり、傷つけたりしてしまいがちです。
頭の中で一人で仮想敵をこしらえて、「こう言われたらこんなふうに仕返ししてやろう」と戦ってくたびれてしまうこともあります。
炎をぼんやり見つめていると、そういう自分の「考え」も、まるで映写機で映し出された映画のように、ちょっと距離をとって眺めることができます。
「映画」と書きましたが、「物語」と言い換えてもいいかもしれません。
「私はこんな人間だ(そういう人間になりたい、なるべきだ)」
といった自己概念に関わる物語もあれば、
「なんで私の身にあんな辛いことが起こったのだろう」
「なぜ辛くても生き続けなくてはいけないんだろう」
「どうして私は人から愛してもらえないのか」
といった生きることの「意味」を問うようなストーリーもあります。
そういった物語は、人が与えられた現実を抱えて、意味を感じながら生きていくために必要なものです。
でも、ときに物語は、ゆがんだり、硬直したり、力をなくしてしまい、
その人の「いのち」にそぐわないものになることがあります。
「きっと私は、また人から見捨てられるに違いない」
「どうしたって幸せになんてなれっこない」
「自分は生きる価値のない人間だ」
そんな物語に縛られて生きていると、現実もそのストーリーの通りになってしまうことがあります(被害妄想とドラマ三角形)。
焚火の炎は、私たちが意識的・無意識的に生きている物語を映し出してくれるスクリーンのようなものです。
「おやおや、自分はまたこんなひがみ虫の物語に取り憑かれているな」
「被害的になって、悪いことばかり考えてるじゃないか」
といったことに気がついて、
「今はこの物語は必要ないから、火にくべておこう」
と手放すこともできるかもしれません。
そして、薪がパチパチと燃える音や、夜空の星の光、森の中の風や動物の物音といった今・ここの現実に触れることができます。
この頃の臨床心理学や精神医学では、仏教に由来するマインドフルネス瞑想についてよく取り上げられています。
- 今この瞬間に、価値判断をすることなしに意図的に注意を向けること
- 今すでにそうあるものをただありのままに感じる、努力を伴わない活動
- 行為するモードから、存在するモードあるいは無為のモードへと移行すること
- 次の瞬間に今と違う何かが起こって欲しいと思う気持ちを放棄して、今ここに立ち止まること
- 自分の存在の核と親密さを開拓すること
マインドフルネスを臨床分野に持ち込んだ一人であるカバットジンは、マインドフルネスをこのように定義しました(マインドフルネスと「ある」こと)。
こうしてみると、焚火もマインドフルネスや瞑想と似て、何かをするために行うものというよりは、「存在する」モードに近いようです。
もちろん、煮炊きをしたり暖をとったり、といった「目的」はあるのですが、夜にじっと火を見つめているときには、私たちは「(ただ)存在するモード」に触れているように感じます。
焚火のときにも、あれこれ考えたり思ったりしているのですが、ふっと頭の中の映画やおしゃべりが静かになる瞬間が訪れます。
今回は一人で焚火をしましたが、何人かで火を囲むのもまた得難い時間です。
「カウンセリング」も、ずっと昔にさかのぼって原初の形態を想像してみると、たぶん誰かが火を焚いているところに悩みを抱えた人が訪ねてきて、いっしょに炎を見つめながら(あるいは自分の内側の物語を見つめながら)、ポツポツと語り、聴くといった、そんな営みだったのではないでしょうか。
ラコタ・インディアンの言葉では、「火」は同時に「幸せ」も意味するのだと聞いたことがあります。
「お前の火は今、ちゃんと燃えているか」
という話は、「お前は今幸せなのか」といったことも含んでいるのだそうです。
炎を前にしばらく過ごすということは、自分の存在や幸福について思いを馳せるひとときにもなるのかもしれません。
寝袋にくるまって星空を見上げながら眠るのは、ちょっと寒かったのは確かですが、とてもいい時間となりました。